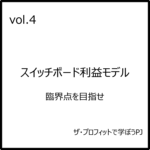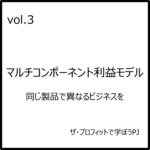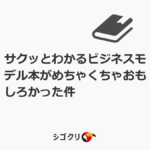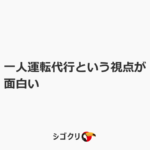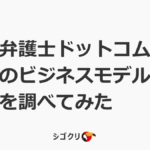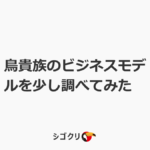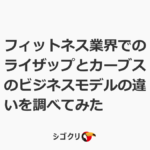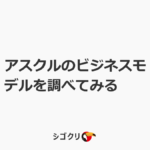Vol.7 利益増殖モデル
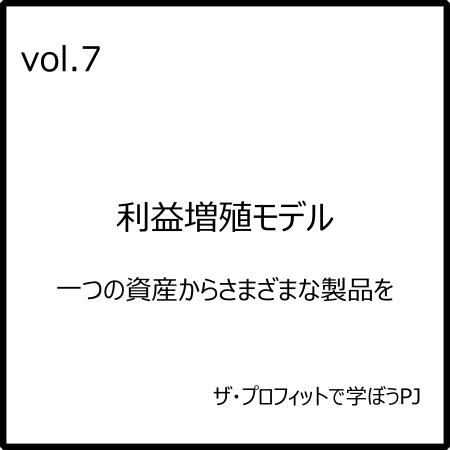
利益増殖モデルは分かりやすかったです。
技術などコアなものから別製品を企画して作っていくことで、どんどん何倍も利益を拡大していくものです。ここでは売上を拡大の方が直観的な感じがします。
利益増殖モデル
物語の序盤は、スティーブが先回のブロックバスター利益モデルについて考えてきていて、それをチャオが添削して凹んでいるところが象徴的です。
この利益増殖モデルは、一つの基礎的なアイデアを膨らませて色々なものに加工していくというものです。
本書の中では、
- ディズニーであれば、ライオンキングについて、ブロードウェイのそれと、DVD、ランチボックス、テレビゲーム、アトラクションなどとキャラクターものはわかりやすいですね
- ホンダであれば、自動車、オートバイ、芝刈り機、ボート、工業用モーターなど。最近は飛行機も作っていたかなと。
図には、基礎から技術や資産、知的所有権などその他の利益形態を生むというイメージが書かれています。
スティーブの疑問に、Vol.3マルチコンポーネント利益モデルと一緒じゃないか?という突っ込みがありますが、チャオは似ているが違うと答えています。
マルチコンポーネント利益モデルは、コーラというものを場所を変えて売ることだったり、ホテルの客室、本の販売形態の違いなどで、これらは同一のものを違う形態で売っていることになるため、異なります。
とはいえ、実際は売り方が異なるとか、売る場所が異なるという意味でかなりまとめられやすい概念だなと感じました。
本章は物語的には、スティーブがチャオが質問が多くて止まりがちなところにイライラしているシーンが象徴的に描かれています。
他には、この利益増殖モデルのポイントは、
- 繰り返しアイデアを使うことで開発コストが下がる
- それにより成功の可能性が格段に上がる
ということが書かれています。何度もコアなアイデアを使うことで成功確率が高く、かつコストも低いという形ですね。
本章から学べること
この利益増殖モデルというのは、モデルかというとわりと当たり前に自分であれば考えていくことが多いです。名前をつけたところ余計分かりづらいという印象も受けます。
例えば、文章を電子書籍で売ることと、PDFで売るのはほぼ一緒ですが、ブログで売るか、noteで売るか、それともメルマガ有料で売るか、はマルチコンポーネント利益モデルと言えそうです。
ただし、文章スキルを持って、取材インタビューの仕事をして記事を書く、または編集をして雑誌を作ったり、人の文章の添削をしたり、キャッチコピーや作詞をしたり、プレゼン資料を作ったりなどは利益増殖モデルといえそうです。個人でシゴトを作るとはこういった利益増殖モデル的に考えないと辛いというか、広がらないという感覚もあります。広げればいいわけではないのですが。
イラストが描ける場合、展示会を行うのか、ある世界観に沿ったものをガンガン描いていくのか、それとも似顔絵を10分で描いてお客さんを開拓していくのか、色々と考えられます。
このように個人や小さな会社がシゴトを作る、事業を作るにはこのモデルの考え方はいたって普通にあるのではないかと感じました。取り立ててこれが「利益増殖モデル」だということはなかったのですが、大きな企業でこれらをやられるととても小さいところはまともにやって勝てることはなさそうですね(笑)
おわりに
本章の最後のあたりに、スティーブの自問自答で、
はたして自分は彼を正しい方向に導いているだろうか。これから彼は、世界と渡り合うことができるだろうか。
(ザ・プロフィット、P.107から引用)
となっていて、村上春樹の小説か、何かの哲学ストーリーかと思えるようなフレーズです。これは、師匠、先生であるチャオがどう生徒を指導していけばいいか、そういう悩んでいるシーンを切り取ったともいえますが、指導者は大変ですね。
ザ・プロフィットはチャオとスティーブの会話がメインで読みやすいですが、その中にこのような指導の仕方というか、チャオ目線、またはスティーブ目線の「地の文」が解説的に書かれていて、客観視出来るのが面白いかもしれませんね。他にもありそうな書き方ですが。
次回は、起業家利益モデルです。
筆者プロフィール

- 「シゴクリ」運営者。アイデアの力でお客様に貢献するゼロイチ大好きアイデアマン。ビジネスアイデア相談実績等は200超を超える。好きな言葉は三方良し。詳しい自己紹介、仕事実績も合わせてご覧ください。お仕事メニューやお問い合わせはお気軽にどうぞ。
最新の投稿
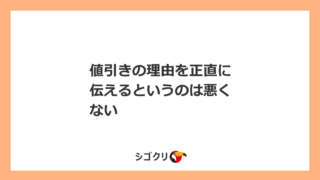 アイデアネタ2024年4月23日値引きの理由を正直に伝えるというのは悪くない
アイデアネタ2024年4月23日値引きの理由を正直に伝えるというのは悪くない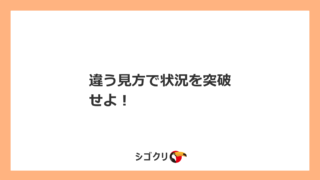 アイデアネタ2024年4月23日違う見方で状況を突破せよ!
アイデアネタ2024年4月23日違う見方で状況を突破せよ!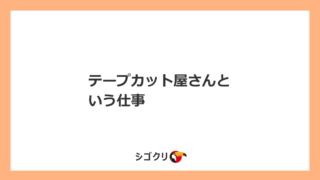 アイデアネタ2024年4月19日テープカット屋さんという仕事
アイデアネタ2024年4月19日テープカット屋さんという仕事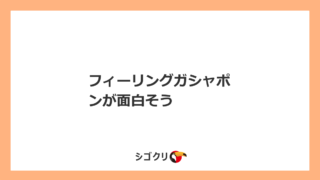 アイデアネタ2024年4月18日フィーリングガシャポンが面白そう
アイデアネタ2024年4月18日フィーリングガシャポンが面白そう