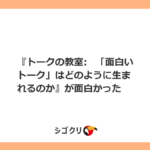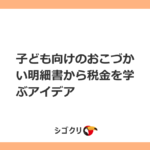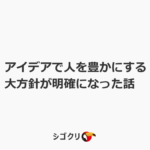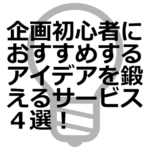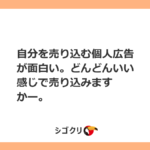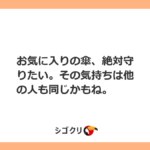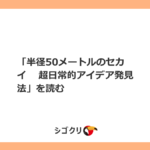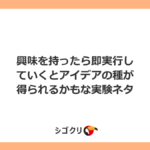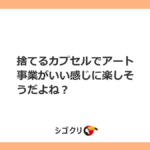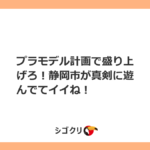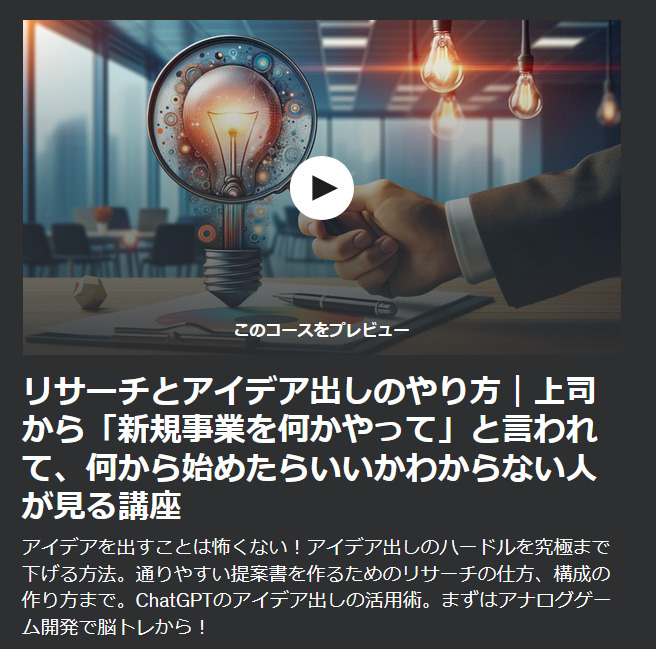販促コンペのグランプリ作品から学ぶ
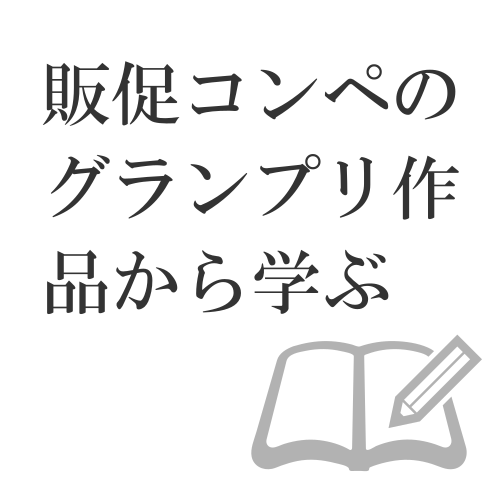
アイデアを出すために、人のアイデアをどんどん参考にすればいいと思います。アイデアそのままやっちゃだめですけど、そこからエッセンスを得て考え方を得ていけばいいかと。
今回は、販促会議という集客・プロモーション・売上げアップのための企画コンペの受賞作品を見て学んでみましょう。骨太のアイデアがこれでもかと刺さりますね。
目次
販促コンペとは
販促コンペは2010年から行われているコンテストです。企画書形式で協賛企業の課題を解決するアイデアを提案して戦うものです。
イメージ的には宣伝会議のほうが有名ですが、マーケティングや販促という点では販促コンペかなと感じています。
過去の受賞作品から学ぶ
第一回から受賞作品はスライドシェアで公開されています。
ただログインしないと過去の受賞作品自体の一覧は見えないようです。グランプリだけ見ていきましょう。
第一回グランプリ
これはコカコーラのペットボトルに、サインペンで文字を書いて、飲み終わったらメッセージが出るというアイデアです。コーラが入っているときはコーラ色で見えない(シークレット)であり、飲み終えると見える(メッセージ)わけです。プレゼン資料も無駄がなくメッセージを伝えたら面白いでしょということを伝えてくれています。
このアイデア自体は2011年ですが、メッセージを書いて渡すというのは、普通に考えると「見える白いラベル」に書いて渡すみたいな感じがします。あと、ペットボトルに文字を書くってなかなか抵抗があるのでそこに気づかないなあと感じました。
調べると、発案者の菊池さんが発想したきっかけを語っています。
(前略)
まず、「誰かにあげる」という目的なら自分も買うかもしれないと考えました。そこからメッセージをマジックで書いたら、文字が見えないのでシークレット・メッセージになると思いつき、友人にやってみたら実際にうまくいったので、この企画が生まれました。
売れる「販促アイデア」の企画・発想術~販促コンペ・グランプリ受賞者 座談会~ から引用
自分が買うという場合、「誰かにあげる」というプレゼントなら買うなあという視点から始まり、そこからプレゼントだから「何かメッセージ添えるか、ならここにかいちゃえ」ということで生まれたアイデアということですね。
ちなみに、このアイデア自体は、受賞企画が商品化・漫画化も!「第5回販促会議 企画コンペティション」作品募集開始にあるように、別冊フレンドの漫画の中にも出てきたようです。面白いですね。
第二回グランプリ
このアイデアは朝日新聞を読むために、しかも親子で一緒というところから、バトルゲームという仕掛けを提案しています。バーコードバトラーなどを知っている人には懐かしいネタですが、それを新聞でやる、また使うものはこどもが持っているであろうゲーム機を使うというところが面白いですね。
とくに「強いニュース教えてよ」という会話はありえそうで、しっかりと企画が浸透した後のイメージが作られているのが見えてきます。
ゲーム自体楽しいとか面白いとかこどもにやらせてみるとかは「わりと出てくる」アイデアでしょうが、それをフックにして新聞をさりげなく読むという仕掛けに持っていけるか。スライドさせるというのが一つのアイデア出しのコツではないかと感じました。
第三回グランプリ
今回も朝日新聞ですが、新社会人向けの購読アイデアです。このアイデアは、仕送りという親がこどもにするというところと掛けて、朝日新聞をこどもに親が贈るというものです。面白いですね。
新聞購読者は減少していると聞きますが、実際に読む機会がないことだったり、この企画ではお金がないということも代弁しています。その中で、親から新社会人なんだから、最後だよみたいに贈るという親心をついたかなと思わせる企画です。
新聞購読者を増やすにはどうすればいいかというお題がある時、単にCMを打ちましょうとか、広告を出しましょうとか、試読をたくさんやりましょうでは簡単に生活者は動いてくれないわけですね。というかそれはアイデアというよりも、お金を使うキャンペーンアイデアの一つといったほうがいいでしょうか。
ではどうすればいいか。ここでは、新社会人の気持ちをくみ取り、想像し、親からの贈りものとすればいいのではないかという気づきを得たのかなと感じました。
第四回グランプリ
このアイデアはチェキを買って使ってもらうためのアイデアです。そのために、赤ちゃんの写真を生まれた時から1年間、つまり365日撮ってあとでアルバムにしたり、展示会をしていくという見せ方です。
アナログな写真の良さという意味で、チェキをしたらすぐメッセージを書いて気持ちを書いておくということです。これはアナログの強みですね。デジタル写真にコメントはなかなかつけづらい印象です。
発案者の瀧澤さんが、ブログで企画書の解説をしています。
販促会議企画コンペ2012 「365チェキ!」企画書公開&解説
この中で発想の源ではないかなと思ったのは、
- デジタルカメラの便利さでもしかして想いが入ってないのではないかという漠然とした不安
- 自身が出産を目の当たりにした経験からのこどもの成長記録をしたいという強い動機
というところです。面白いのは、このチェキを提供するアイデアとして「産婦人科への無償提供」というネタですね。
こういった企画プレゼン資料を見たことがないとか、考えたことがない人であれば「そんな発想できない」と思うかもしれませんが、どんなクリエイターであれ一人の人間です。自分の体験や感情は同じようにあるわけですね。くどいですが、広告すればいいとかでなく、具体的なアイデアに落とし込んでそれがそれなりに出来るもので、同時に課題解決につながっていないとまず受賞以前に、審査を突破できないわけですね。
第五回グランプリ
ドミノ・ピザのネット注文を増やすアイデアということで、個人的に非常に好きなアイデアです。ピザパーティーでありがちな、欠席する人の申し訳ない気持ちと、参加している側の気持ちをうまくミックスしている点が秀逸です。その点を思いついてもなかなか今回の「おいしい欠席」という代わりピザというものに昇華できない気がします。
最後ページにある定番化もなるほどと思いますが、自分で注文して食べるでなく、誰かに食べてもらうためにという需要を発見することになるかもというのは面白いアイデアだなと感じました。
ネーミングも面白いですね。ダブルミーニングというやつで、1つは贈ってもらったピザパーティー参加者は「美味しい」ピザが食べられるし一つ増えるし嬉しい。もう1つは欠席する側はみんなにメッセージ+写真を見てもらえることで注目を浴びられるから「おいしい」というわけです。
もちろん、注目を浴びたくない人もいるのでおいしいとは一つのパターンであり、ごめんね!というだけのパターンも想定されています。さすがですね。
ピザ宅配を増やすということで、割引キャンペーンだったり、季節やカレンダーに合わせた販促は普通にあります。ここで求められるのはそういうものでなく、利用者がどういう気持ちでいてどういうことを考えているかを考え抜くことが求められます。それは非常に複雑な気がしますが、一方でシンプルに「ピザパーティーいけないわ、ごめん!」という点からスタートするアイデアかもしれません。
第七回グランプリ
第六回はグランプリがなかったので飛ばして、第七回です。
お題にあるように、養命酒を40代の母親にどう売るんだ?という疑問しかなかったのですが、その読み解き方が面白いです。
こどもが頑張る時に親は頑張らずにはいられない。象徴的な受験シーズンを狙ってボトルを修正して、ラベルに文字も入れるようにできるというアウトプットになってきます。そうくるかー!というアイデアですね。
とはいえ一方で養命酒自体を一体誰が飲んでるか全くわからんというところで、こういうお題を考えるのは難儀というか難しいですよね。本名酒面白いですね。
第八回グランプリ
電子書籍を読みたくなるということで、回し読みというアイデアをうまくつかったものです。紙は回し読みや貸し借りはできますけど、電子書籍は・・・。キンドルで貸し借りはamazon.comなどアメリカならあるようですが、日本ではないですね。実機や端末を渡すしかないんですよね。
本アイデアでは昔流行ったバンプ?だったかな、スマホを振ると相手に貸せるという仕組みです。直観的で面白いですね。
一方で、本を良く読む人はそれなら買うわといって買って読むのかなと。このあたりを考えると「この本いいから読んでみたら」というオススメをする環境がどこまであるかですよね。そっちの環境づくりをリサーチして、拾っていっても何かアイデアが出そうですね。読書会とかイベント化されてないが、人との本の会話がどれくらいあるかってことですね。
第九回グランプリ
干支のかわいい子たちに見た目を変えることで、違和感から変えさせるということですね。面白いです。ただあえていえば、放置する人は干支が一周したり(笑)、数年ずれていても使うかもとか。まあ少ないでしょうが。
一方で、干支を意識するし、カレンダーというか常にあるけど気にならない(ビジュアルが可愛い)、邪魔しないのがいいなあと感じました。あれば買おうと思ったくらい好きなアイデアです。
コストを掛けているわけではないのに、課題を解決しているからですね。
第十回グランプリ
インバウンドで訪れる外国人観光客に向けて、空港で両替できない時にブラックサンダー1個を小銭32円で替えられるというアイデアです。面白いですね。これによって、ブラックサンダーを食べてもらうきっかけが増えそうですね。
このアイデアも、小銭が両替出来ない空港にてどうしようかという状況で、32円という小さな金額とブラックサンダーの安価という特徴をうまく突いているといえます。
解説されればそうなんだけど、ここに気づけるか、それで課題解決になるかというところまでいくと、簡単にはいかないですよね(笑)
第十一回グランプリ
女子高生が学校に持っていっても不自然ではない、という文房具に入り込んでいるのが面白いですね。
アイデアとして、学生だから文房具というところに目を付けても、文房具型の化粧水というところまではなかなか行かないなあというのを感じました。そこがアイデアジャンプしていますよね。
結果から見て後でいくらでも言えるわけですが、見つけたアイデアを形に出来るレベルに落とし込むのはまあ大変ですよね。
第十二回グランプリ
コンタクトレンズを洗浄するというところを非常に面白く捉えたアイデアですね。猫も可愛いですし、日常に入りそうだなあという予感しかしません。
行動として面白いのは、洗浄しないと!で買う人はほぼ居ないはずで、啓蒙活動になっちゃうんですね。ケースに目をつけてそこで光れば気づくというところで、普段の行動としてコンタクトケース所持は変わってないわけですね。
当然そのケースが可愛くない→可愛い猫にするという動機にもなりえるので、自然な販促ができそうです。あと値段や技術的なことはおいておいて、コンタクトに対してブラックライトを当てるという発想は考えたことがないですし、それが「猫の目」とアナロジーと言いますか、類推したのか分かりませんがなかなか出来ないところだなと感じました。
面白いアイデアですね!
第十三回グランプリなし
13回目はグランプリ該当がなかったようです。というわけで、この回は省きます
【第13回販促コンペ結果発表】 応募数4631点の中から、ロート製薬、ミニストップ、聖隷福祉事業団の3企画がゴールド受賞。グランプリは該当なしに
第十四回グランプリ
オセロの遊んで見たくなるアイデアが受賞。
スポーツ実況で盛り上がるというネタです。面白いですね。そんなオセロならやってみたいですね!オセロをどう面白くするかって少し考えたのですがとくに出ずだったので、さすが!というところですね。
第十五回グランプリ
セットリストをレシートでということなんですが、コロンブスの卵っぽいですね。でも素晴らしいアイデアですね。カラオケ行ってみたくなる!
販促コンペから学べること
何回かコンペアイデアを考えたことがあるのですが、普通に手強いです(笑)
なぜだろうかなと思ったら、
- 協賛企業の商品やサービスの理解が不可欠
- 当然知らないなら試す、知っているならなぜ知っているかを深堀する
- 企業が抱えている課題をどう感じるかを考える。自分はそう思った?そうでもない?どういうイメージがある?など
- 自分がお客さんなら、Aさんが買うなら、Bさんならどうするか、ターゲットを想定したり、各プレイヤーがどういう心理か、状況か、コミュニケーション手段はどうかを吟味する必要がある
- その上でアイデアとしてこうしたらいいのではないかを考える
- それらが当初のお題である課題に対して、解決策となっているか。また、現実的であるか、不自然でないか、コンセプトと合致しているか
を考えるというよりも、考え抜くという感じだからなんですよね。
最新の第10回では過去最多の4,088点の応募があり、受賞は7点という少なさです。1000に1個ちょっとくらいの確率ですからね。ファイナリスト自体は40点くらいあるように見えますが、まあ何にせよものすごいバトルですね。
ここが大事じゃないかと一つだけ言うならば、
利用者視点でのコミュニケーション
かと思います。顧客目線とか、利用者目線とか言い尽くされているのですが、その視点で本当に考えられる人は稀です。なぜならこれらのコミュニケーション、つまりお客さんとして買う時、商品をどう買うか、サービスをどう受けるかは常に変わるからです。
何かをものを購入するというのも、複雑化していて、買う場面、決済、その時の気分、店員対応、雰囲気、楽しいかどうか、ありとあらゆる要素があります。これらを抽象化して理論的にいえることはあるのでしょうが、お客さんである利用者の心が動くというのは、理屈ではなく、「情緒」であり、共感や感動ということでしかありません。
その共感や心が動くことは、人それぞれ異なります。だから万能なアイデアがあるわけではないですが、とはいえ見定めたターゲットに対して刺さるものは、つまり心を動かせる何かはあるのではないか。こうしたらいいのではないかがアイデアの核となります。
どうすればこの商品に気づいてくれるだろうか。どうすればサービスを試してもらえるだろうか。そんなことを考え抜いた先にあるのが、こういった販促アイデアだろうと考えています。
立派な販促アイデアじゃないと駄目?
ここでは狭い意味で販促コンペで評価されるアイデアが良いと捉えていますが、実際の世界や社会はそうではないですよね。なんでこれが?というようなことの連続です。それだけではないですが(笑)
あえて立派な形式ばった、悪く言えば優等生的アイデアといえるわけですが、それもいいと。一方で、はちゃめちゃなアイデアで共感されたり、応援というのもあります。無謀なアイデアなどですよね。
例えばですが、こちらの記事大学生が開発した「勉強しないと止まらない」目覚ましアプリが内定10社につながった話と、運用費がほぼゼロ円でも優秀だった「アプリ意見箱」3つの効果は普通におもしろいですが、さらっと記事最初の加藤さんが、生徒にモーニングコールをしていたということが書かれています。生徒にモーニングコールをするのが一般的かはおいておいて、すごいなあと。そこからアプリ化までいくのも面白いです。
このようなアイデアを販促コンペと比較するのはナンセンスともいえますが、こういった生徒のことを考え抜いて、モーニングコールが結構勉強効果出るからいい、けど続けるの大変、ならばアプリで目覚まし時計にすれば生徒でも出来るじゃんというアイデアも素晴らしいわけです。
お題が提示され、それに対してどうですか?と提案するのでなく、「なんかどうしよっか、こうしたらいいかも、じゃあやろう、やってみたらよかった」という流れ、これこそまさに日常の仕事における課題発見と解決のアイデアがセットになったものだと思います。
むしろ冷静にとらえている人ほど、販促コンペは実績や名前を知ってもらうためとかそういう意図でやる人が多いのかなと想像しています。実際に役立つとかスピード感とかって、自分で考えて自分で実行をすぐ出来たほうが最も早いですから。ただ、それを組織なり人にやってもらうとか、仕組みとなると話が別です。
そういう意味で、日常で見つけた課題を解決するということ、それがまさにアイデアを考えて形にするということにほかならないと。
「すごい」賞なり評価を受けることと、全く評価はないけど「役立った」といってもらえるものと、「見られる人の数」などは異なるだけで、基本同じだと僕は考えています。あえて使い分けたり、違いを意識していけばよく、それ以外のものではないということですね。
おわりに
アイデアの可能性というと笑われるかもしれませんが、アイデア一つとってもこれだけのことが出来るんだという可能性を感じます。やはり販促に限らずアイデアで人が動くこと、形になって思い描いた世界やイメージになっていくことは超面白いなあと。
今回はグランプリだけしか見ませんでしたが、受賞作品はその他にもあるので、ぜひ気になった方は新規登録などして見てみてください。自分もいけるぞ!と思った方はぜひ来年のコンペにチャレンジしてみてはどうでしょうか。
考える中で色々とアイデアが深まったり、気付きが出てくるのではないかと思います。そういうきっかけにもなりますしね。
筆者プロフィール

- 「シゴクリ」運営者。アイデアの力でお客様に貢献するゼロイチ大好きアイデアマン。ビジネスアイデア相談実績等は200超を超える。好きな言葉は三方良し。詳しい自己紹介、仕事実績も合わせてご覧ください。お仕事メニューやお問い合わせはお気軽にどうぞ。
最新の投稿
 アイデアネタ2024年7月26日思い出はデジタル化はできないが、思い出のきっかけは常に残せるのかも。
アイデアネタ2024年7月26日思い出はデジタル化はできないが、思い出のきっかけは常に残せるのかも。 アイデアネタ2024年7月25日るるぶの豆本化に学ぶ。小さくしてみたら面白いかも。
アイデアネタ2024年7月25日るるぶの豆本化に学ぶ。小さくしてみたら面白いかも。 思考・考え方・メモ2024年7月25日キャリアモデル開発士認定証頂きました。
思考・考え方・メモ2024年7月25日キャリアモデル開発士認定証頂きました。 思考・考え方・メモ2024年7月25日シゴクリラジオゲスト回。キャリアモデル開発の長沼さんから刺激をもらいました!
思考・考え方・メモ2024年7月25日シゴクリラジオゲスト回。キャリアモデル開発の長沼さんから刺激をもらいました!
リサーチとアイデアの出し方講座
気になる方はハードルを極限まで下げているのでチェックしてみてください!