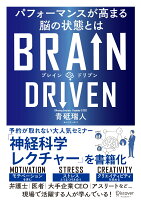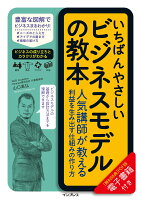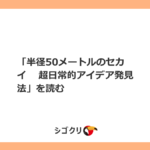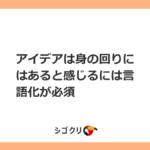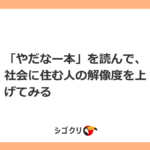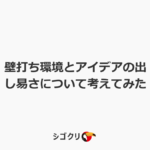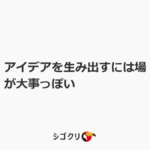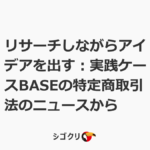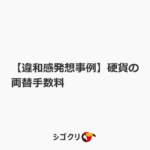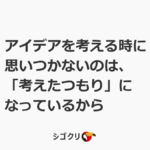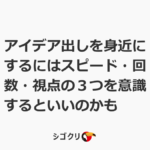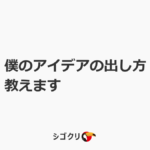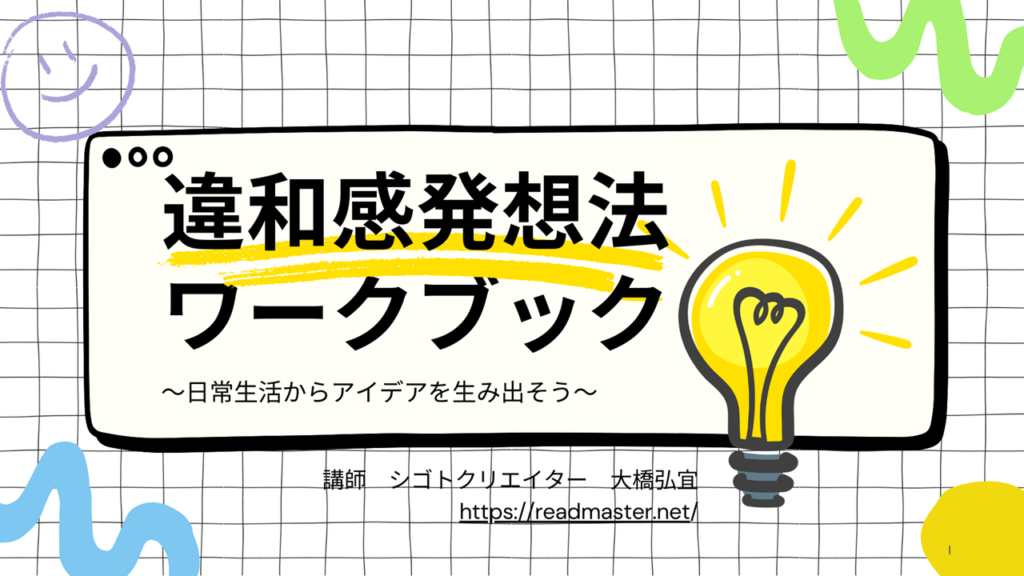違和感が発想に使える根拠をメモしていく
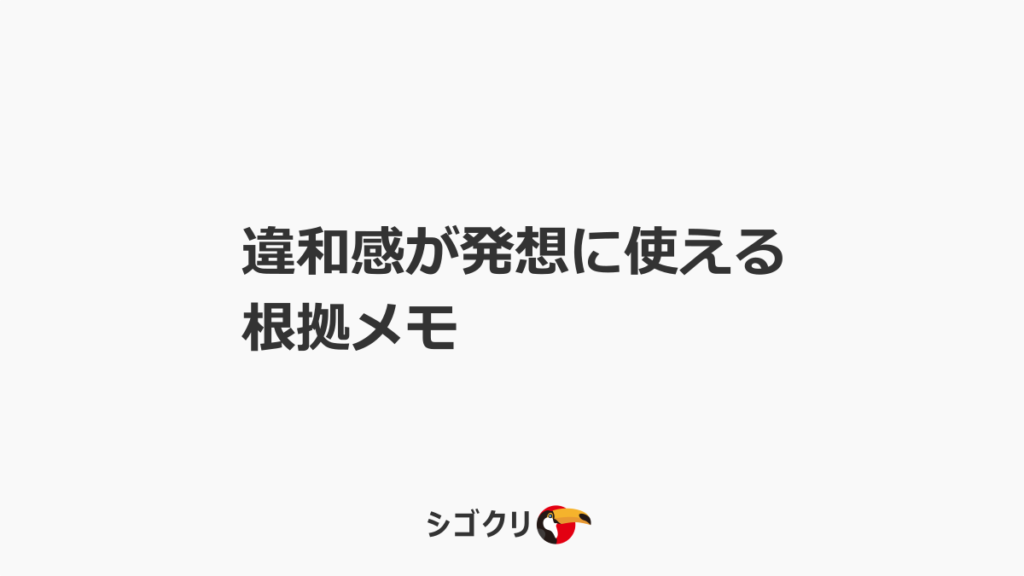
違和感発想というのは、僕が勝手に言ってるだけですが、とはいえ色々な人も「違和感」が使えるということをよく目にします。
ここでは、僕が暴走しているのでなく(笑)ほかの人も言っているんだという言及をソースとして示す意味で、説得力も増すはずなので、それをメモ的に載せていきます。
目次
違和感が発想に使える根拠達
違和感発生は脳に根拠
違和感を覚えるのは、脳に根拠がある。その根拠の探究が、面白い発想や新たなアイデアにつながる可能性がある。そこに至るには、その分野にどっぷりと浸る必要があり、自己の内側の反応に興味を持つことが求められる。違和感の正体に気づくことができれば、それについて考え、言語化し、非言語的な絵や音楽などに表現することもできる。それが創造や新しい着想の起点につながる可能性があると考えると、違和感はクリエイティビティの宝箱かもしれない。
青砥瑞人. BRAIN DRIVEN パフォーマンスが高まる脳の状態とは (Kindle の位置No.3335-3339). 株式会社ディスカヴァー・トゥエンティワン. Kindle 版.
作家の渡部昇一さんの「人間らしさ」の構造(講談社)からも引用されていて、非常に興味深いです。
真珠貝は貝殻の内側にはいった砂くずが痛いため、それを包む成分を出しているうちに真珠を作り、詩人は自分の心の痛みをもととして詩を作るという。貝にとっては、砂くずは異物である。それが貝にとっては違和感なのであろう。しかしそれがもととなって美しい真珠が貝殻の内側に形成されるのである。人の心もおなじだ。強烈な違和感が偉大なる人物を作るもとになるのである。
青砥瑞人. BRAIN DRIVEN パフォーマンスが高まる脳の状態とは (Kindle の位置No.3341-3344). 株式会社ディスカヴァー・トゥエンティワン. Kindle 版.
簡単にいえば、脳の機能として違和感を感じるようになっているんですね。そして、真珠貝の話は異物を入れることで、というのはエモいなあと感じます。違うものに触れたりある種「歓迎しない」ものこそ、チャンスかもしれないですね。
起業家は違和感を直視した人
「起業家」とは社会に対する違和感を直視し、自分が理想とする社会のあり方をはっきり定義して、実際に行動を起こした人のことを指します。
山口高弘. いちばんやさしいビジネスモデルの教本 人気講師が教える利益を生み出す仕組みの作り方 「いちばんやさしい教本」シリーズ (Kindle の位置No.503-505). 株式会社インプレス. Kindle 版.
本書的には起業の話でもあるので、起業家となっていますが、やはり何かしら新しいチャレンジをする人の代表である「起業家」も、違和感をしっかり見て向き合っているともいえます。別に誰もが起業家になれとは思わないのですが、こういう精神やマインドセットはいるわけで、またアイデアを出すときのやはり大きなきっかけになるということが感じられます。
違和感は、いびつな力であり、思考を増幅させられる
違和感とは、通常にはない「いびつな力」のことです。それがあったときに、素通りせずにそこに目を留め、それがなんなのかを解き明かしていくことで、アイデアの強い芽が生まれるのです。夏になるとむしょうに聴きたくなる音楽がある。海の家のカップラーメンはやたらとうまい。そういうものは体内、あるいは記憶の中に、気持ちを強く揺り動かすなにかが存在しているということです。だとすると、それはなにかをひも解くことで発見が生まれ、それをもとに思考を増幅させることがアイデアとなっていきます。
樋口景一「発想の技術 アイデアを生むにはルールがある」、朝日新聞出版、P.82-83
本書は発想の仕方をかなり分かりやすく書いていてそのとおりだと感じています。違和感についても、「いびつな力」と著者なりの定義をしていて、それこそまさになかなか言葉では言えないが、たしかに力としてあるということでしょう。
ここでは、自分の記憶や体内にあるものがあるけどある違和感によって気付いてそこを掘り下げていくと、思考を増幅させることができるといっています。まさに違和感からアイデアが出るということが明記されていると。
これを見て僕は興奮しましたし(笑)何よりそうだなあ、首肯!首肯!と首を何度も縦に振ったものです。
違和感を起点に仕事を作るとアイデアに熱がこもる
こうしたワークショップをすると実感してもらえるのですが、多くの人は日頃「自分」起点で仕事をしていません。一方、「自分」の「偏愛」や「違和感」を起点に「仕事 work」をつくるとアイディアに熱量が生まれます。アート・シンキングは熱量にあふれています。
若宮和男「ハウ・トゥ アート・シンキング 閉塞感を打ち破る自分起点の思考法」、実業之日本社、P.177
本書はアートシンキングの話というよりも、実際にはロジカル過ぎると結局似たようなものになるし、デザイン思考は悪くないけどいきなりそれが使えるわけではない。わかりやすかったのは、アート→デザイン→ロジカルみたいに使うフェーズが異なるというところです。アート的なものというと、自分の欲するとか表現的なことといっていいわけですが、上であれば「偏愛」など自分が好きでしょうがないもの、偏っているけど気になってしまうもの。そして違和感もあるわけですね。
著者からすれば、そういう偏愛や違和感を基に仕事をつくるというのは起業家だけでなく、仕事をする場合ですよね、アイデアに熱量が入るといっています。逆にいえばそういう偏愛や違和感がないとアイデアはかなり寂しいものになるわけですね。むしろ、熱量がないのでうまくアイデアを実行できないことが多いはずです。
また本論とはずれますが、自分起点で仕事をするだけでぐっと違った生き方、働き方になるわけですが、そういうのも違和感やアイデアといっていいわけですね。
違和感を見過ごさず、アイデアの種とする
それよりも、自分を守りすぎる気持ちが創造性の妨げになることのほうが問題です。保身のため、直感よりも理論や常識、データを過剰に重視して、新たなチャレンジをするチャンスを失ったり、「これって何か変だな」と違和感を覚えても、なぜ違和感を覚えるのか、それがビジネスにどんな影響をもたらすのかを深く考えず、違和感自体をなかったことにしてしまったりすることはままあるでしょう。実はその違和感を持ったところに、新しい製品やサービスの種があるかもしれないのに、見逃してしまうというのはよくあることです。
前刀禎明「学び続ける知性 ワンダーラーニングでいこう 」、日経BP、P.196
違和感自体は覚えているのに、そのまま見過ごす。これについては違和感発想WSでも受講者から聞く話です。違和感って大事なんだろうけど、そのままにしていた。または通り過ぎていたというわけですね。
違和感自体が必ずヒントとはもちろん言わないですが、多くはヒントになるし、種になると。それが全く自分の手掛けるビジネスや仕事と違えば違うほどそれは強力なヒントになるはずです。なぜそれが気になった?考えてみるといいわけですね。
概念化した情報とのズレに気づく
北川氏は、共感できる感覚を磨くため日頃から努力している。その方法の1つが、行き先を決めずに街を散策することだ。「駅に着いたら、停まっているバスに乗り、気ままに降りる。見なれた景色も歩いてみると違って見えてくる。概念化していた情報とのズレに気づくと、それが発見になる」と言う。
日経デザイン2016年2月号 P.42
GRAPH代表の北川一成氏のコメントです。これはまさに違和感を得ていると感じました。あと本誌で面白いのは、ひらめきとは「忘れていたことをふと思い出すような感覚や瞬間」と同じという話です。これそうだなあと思ったのですが、閃くより「思い出す」方が誰でも出来そうだなとも言えそうです。
上のコメントでは、概念化した情報、つまり自分の固定概念に近いですが、例えば「駅」には人がいるけど、全くいない「駅」だと無人駅とか、廃墟駅、秘境駅みたいなのがあることに気づけないですよね。電車的なものなら、電気で走ると思っていると「上に架線」がついてない、ディーゼル駆動のワンマン列車は想像できない。
つまり、そうやってズレを検知していくと、いかに自分が知らないか、見えてないかが見えると。これを象徴的に示しているのが散策というだけで、散策しなくてもできるし、自分の概念が固まっていると意識するだけで、何か違いですよね、つまり「違和感」がないかを意識できると解釈できました。
自分の視点を作るためのメモ
吉泉氏が枠組みを見つけるために行っているのが、独自の「自主研究プロジェクト」だ。日頃からあるテーマについて考え、プロダクトを試作していくことで、クライアントからの依頼を受けるときのアイデアの”引き出し”として蓄えてく。テーマはさまざまで、吉泉氏は日頃から「本を読んで感じたこと」「街を歩いていて目にとまったもの」「クライアントとの会話の中で気付いたこと」などをパソコンやスマートフォンにメモとして書き込んでいる。
「メモを貯蓄する一番の目的は、『自分の視点を作る』こと。「自分の視点があれば、ニュートラルな立ち位置で物事を捉えられるし、クライアントの業界が縛られている枠組みも見えやすくなる」(吉泉氏)。
日経デザイン2016年2月号 P.52、太字は筆者注
TAKT PROJECTの吉泉聡氏のコメントです。
激しく同意だと思ったのが、太字部分です。僕も同じですが、依頼があるからやるのでなく、なくてもストックしていく。これは常にやっています。それに関してやはり気になったものを、とくに目に止まったものをというのが違和感に近いですかね。
もう一点自主プロジェクトはめちゃくちゃいいですね。吉泉氏の場合はプロダクトとしてコンセプト的なものとか本当に作っているのがすごいですが、僕はそういうものは作れないので、サービスなり自分なりの実験したこと成果をまとめたりとなります。実際に今までやったこともアイデアで終わることもありますが、形にしてみてどうなるか?を実験していることやものは長続きしますね。
自主企画を愚直にやること。これは売上にそれがなるわけではないですけど、それができる仕組み、マインドセット、ストックして研究していく姿勢がないとやはり「依頼が来てから」では遅いですし、勉強というかアウトプットが足りない感じを受けます。この自主プロジェクトは何でもいいと思っていて、やはり自分なりの研究をぶつけていくのがいいですね。僕なら違和感発想法とか、アイデア研究とかが近いですが、何が仕事になるのかというシゴトクリエイター的な視点も全然ありですね。
アイデアを思いつきやすい人は違和感を見過ごさない
リクルートワークス研究所の「創造性を引き出しあう職場」の探究というレポートが面白いです。
ここで、P.14図表7においてレディネス=創造性のための準備という解釈と僕はしていますがこれをしている人は、アイデア(ここでは職場において新しいやり方や方法ですね、仕事などで)を思いつきやすいという傾向があることが示されています。レディネス度が高いという意味でのやや文字は小さいですが「仕事に取り組む中での違和感を、見過ごさないようにする」などを含めた4つの項目から分類されていると考えられます。
違和感だけではないですが、違和感を含めた準備ですね、をしていくと気づきやすくなり、アイデアを思いつく。そのために準備が大事ということですね。このレポートは、レディネス→アイデア→探究→提案という形でとくに職場のワーカーの動きということが主題ですが、アイデアを出すということにおいてもほぼ同じことが言えそうだなと感じました。
実際に職場=フリーランスなら自分で設定するだけなので、そこの自由度や強制度のパラメーターは様々ですがどういう状況でもアイデアを出せるかが大事かもしれませんね。心理的安全と共創しやすいかは別という視点も面白かったです。
小さな仮説と些細な違和感で解像度を上げる
ビジネスで課題が解けない理由は、問題が分解されていないから
家庭用ロボット「LOVOT」開発者が語る、「分解力」の高め方
GROOVE Xの林さんの会話として、プロの証左として、これで良いんじゃないかに対してどれだけ違和感を多く感じるかという話をしています。専門領域だと解像度が高いわけですけど、でもそうでない素人の領域でもそれをそれなりにやるのが大事というのも確かになあと感じました。
この違和感自体は説明は合理的にしづらいので、「何か違和感がある」というところを沢山出すこと、かつそれをチームや組織と人と一緒にやるなら説明できれば人は動かせるし、違和感共有して進められますよね。
本記事は解像度の上げ方となりますが、それは分解できているかということでほぼ同じなわけです。そしてそういう分解とか解像度とかってところにおいて、小さい仮説(大きな仮説ではない、これは大きなアイデアでなく小さいアイデアという形で対応している気もします)を立てるのが大事という話もある。
これらをまとめてしまえば、小さい仮説自体が先かとか、違和感が先かとか、解像度を上げるのが、分解するのが先かとか、順序はあまり僕はないと思っていて、違和感が生まれてしまったからそれを検証したり、肌感で試してみていくことが「分解」であり、「解像度」を上げることなんだろうなあと思った次第です。
小さい仮説って言葉いいですねー。
僕らは違和感に生きている
違和感自体は結局は備えついたセンサーであるといって良さそうです。アイデアマンである人はこのセンサーを違和感もですが、色々な刺激をうまく使ってアイデアを出していると感じます。
その気づきを「気付いてないふり」をすることで、色々と本能レベルや違和感センサーもということですが、失ってしまわないか。それこそが不安な気がしますし、生きている実感が減るのではないかという危惧につながります。
気づけば違和感だらけのはずですから、それを殺さず、向き合うことで、どんどんアイデアを出していきましょう。
筆者プロフィール

- 「シゴクリ」運営者。アイデアの力でお客様に貢献するゼロイチ大好きアイデアマン。ビジネスアイデア相談実績等は200超を超える。好きな言葉は三方良し。詳しい自己紹介、仕事実績も合わせてご覧ください。お仕事メニューやお問い合わせはお気軽にどうぞ。
最新の投稿
 アイデアネタ2024年7月26日思い出はデジタル化はできないが、思い出のきっかけは常に残せるのかも。
アイデアネタ2024年7月26日思い出はデジタル化はできないが、思い出のきっかけは常に残せるのかも。 アイデアネタ2024年7月25日るるぶの豆本化に学ぶ。小さくしてみたら面白いかも。
アイデアネタ2024年7月25日るるぶの豆本化に学ぶ。小さくしてみたら面白いかも。 思考・考え方・メモ2024年7月25日キャリアモデル開発士認定証頂きました。
思考・考え方・メモ2024年7月25日キャリアモデル開発士認定証頂きました。 思考・考え方・メモ2024年7月25日シゴクリラジオゲスト回。キャリアモデル開発の長沼さんから刺激をもらいました!
思考・考え方・メモ2024年7月25日シゴクリラジオゲスト回。キャリアモデル開発の長沼さんから刺激をもらいました!
違和感で発想のやり方が学べます
LINE公式アカウント登録で無料で学べます。気になる方はチェックしてみて下さい。