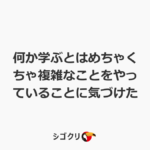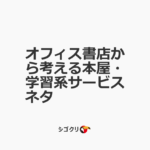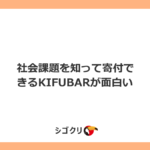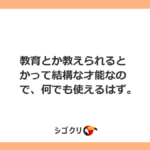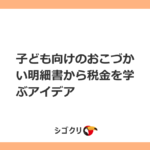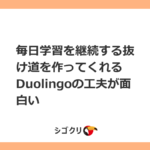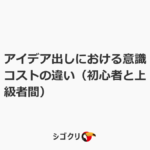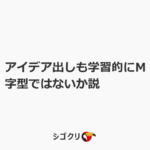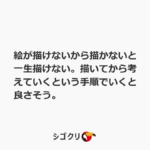manavee(マナビー)の失敗から学ぶ
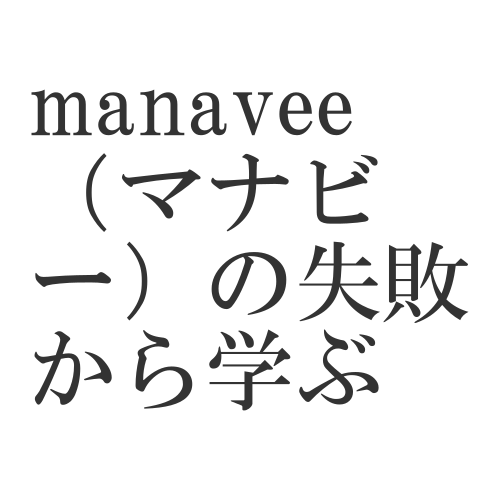
今回はmanaveeという動画型学習サービスの失敗を弔います。僕自身はこのサービスを使ったことがないので、どういうサービスだったかも参考情報からになるのですが、Twitterから流れていて終了自体を知りました。
そのマナビー公式からの終了メッセージ(これがいつまであるか不明です)が熱がこもっていて、非常に学びになると思います。そういう意味で、マナビーは解散はしたが、良い学びで終わったのではないかなと思います。
目次
オンライン教育動画でとくに中高生向けの学校学習だったかなと思います。色々な競合に巻きこれる中で結果的にポジションが築けなかったのかなと思います。
2012年11月頃のプレスリリースを見て正確なところをみていきましょう。
manavee登録ユーザー数1万人突破!! 誰でも無料で受験勉強ができる社会へにもありますが、大学生を中心とした講師が、学生向けに教えるという動画サービスとなります。
ミッションとしては、大学へ行くのに教育格差があることから、その格差是正のためにというところのようです。だからこそ無料で見られるというこだわりがあるんですね。
「お金がかかるのは変」 無料の受験動画サイト「manavee」作った東大生 プログラミング未経験から5万人が使うサイトに (1/4)によれば、manaveeは2010年10月オープン、2013年の3年後には講師約200人が5500以上の動画を公開し、高校生などを中心に約5万人が視聴という規模になっていたようです。
当初スタートした時から基本ボランティアベースで、ビジネス的な視点はあまりなかったように感じますが、代表者が格差を自分としてあったわけではないのにそこに突っ込めたのは結構すごいと思えます。同じ東大の仲間で盛り上がった時のくだりがありますが、多くは盛り上がるけどやろうといってやり切れることがないからですね。
- 講師が現役の大学生(東大や慶応などの有名大学)
- 視聴者は無料で見られること
というのが大きな特徴だといっていいでしょう。
なぜ失敗したか
現在公式サイトは閉鎖のお知らせということで振り返りが書かれています。こういった閉じたサービスで振り返りが書かれているのは稀な気がします。
失敗についてはいくつか書かれていますが、1つはキャンパス制度の失敗、もう1つは事業部の失敗の2つの失敗から、最終的にmanaveeという団体を継続する合理性がないという判断になったとあります。
簡単にいえば、キャンパス制とは大学サークル中心に動画を制作したりしていく動きでしょう。これは大学生が他大学をネットワーク化していくには面白く、ただサークルであるため当然ボランタリーなので継続意義が求められます。単純に2013年にピーク後にどうもうまくいかないというところになっています。
事業部とはスタッフの自主性からチームを組んでプロジェクトとしてやったものの、多くは頓挫してしまったというところで、キャンパス制失敗の次のアイデアとしてチャレンジしたけどダメだったということになります。
公式の反省点から学ぶ
動画著作権をボランティア講師に帰属させたこと
1つ目は、動画の著作権がボランティア講師にあることで、例えば事業として自由に使えないなどがあるということです。これは「ナイーブな良心」という表現をされていますが、山月記ばりの素直さがあるなあと感じます。確かに、ボランティアでやってもらってやった講義動画さえ著作権を団体に渡したら何もないのかなというのは分かります。一方で著作権を学ぶと色々分かるのですが、著作権としてめちゃくちゃすごい音楽があっても聞いてもらう機会や演奏の場、人の耳に届くことがなければ著作権はあるけど何も生まれないともいえます。
つまり、著作隣接権みたいなものです。ただ著作隣接権って芸術性があるものが強く(役者とか)、それがそのまま使えるかは分かりません。少なくともmanaveeという中間者またはインターネットサービスというのがあるからこそ、講義は生きるのでそのあたりは冷静に見ると面白いのかもしれません。
あとTwitterなどで話題にもなるところですが、Twitter上のコンテンツは投稿者に著作権はあるけど、TwitterAPI等正式な利用ならそれらを表示したりは別にいいんですね。というようなAPIであるとか、例外ルールとして自社活動においては当然使うと、そういう感じならいいんだろうなあと思いました。最も活動当初にそう決めてしまってGOしたので仕方がないとは思いますけどね。
ちなみに僕が大学生であったり社会人数年の若者でこのような事業をやったとしたら、ナイーブな良心からうまく事業化はできなかったと思います。あとこういう良心は性格や社会に対する考え方の裏返しでもあるので、うまく長所として活かしたいところですよね。
NPO法人化による保守的な意見が蔓延したこと
事業が大きくなる以上にちゃんとした組織になるということが一つの課題だったことから、法人格を持つということでNPO法人化をしたという話です。それによって2つの課題が出てきたと。1つは業務処理が増えること、もう1つはNPOの理念による保守的な意見が通りやすくなったことと書かれています。
前者は割愛されていてオッケーなのですが、後者についてこれは正直良くわからないのですが、NPOというのは後づけであって、単にメンバーらの力量や考え方の相違ではないかなと僕は感じました。そもそもNPOとかはおいておいて、何かをやろうという時そのミッションなりに賛同したりやる人は文字通り「変化」が求められます。変化すればいいというよりも、柔軟な考え方が求められるわけです。
例えばAという状況では前進だけど、それがすぐにBになるから後退みたいな。でもAとかBとかの判断も自分たちだし、命令というか動きも自分たちでやるので、誰かを責めるとか、どうとかいう暇はありません。例えば「うちは小規模だから仕方がないよね」という愚痴?を言うのはありだけど、それだから愚痴って何もしない人はまずこういう何かを立ち上げられる人ではないわけです。
だからこそ、花房さんは「保守化は予見できず悔やまれる」とあります。確かに当時チャレンジングに仕掛けることが、いやそれのみが特徴であり変えていくにはそれしかないわけで、そこで安全策を取るのはもはや団体意義は薄くなるでしょう。
補助金を受けたことによる事務コスト増大
紐付きのお金を受けたことにより、色々な事務コストがかかり大変だったという話でした。これは花房さんの課題としてビジネスモデルがないとか、要は稼ぐ仕組みが弱いわけです。というか自分もそう思うけどアイデアがない。はいわゆる個人の持ち出しだったので、団体によって寄付や補助金で運用する非営利団体スタイルにしようという狙いのためのアクションだったわけですね。
そのために試したことが結果的にアダとなってしまったんですね。
自身の日和見や一貫性の不足
花房さんは非常に正直な方だというのが分かるわけですが、上の反省点の動画著作権を除く、法人化組織の保守化や補助金の事務コスト増大などは、そもそも自分の中でもなんとなく正しいという社会的な正しさでジャッジしてしまったと述べています。つまり、自分がこれがいいんじゃないかと思っていなかったわけで、他の人や社会が言うならそれが正しいよね、という良くも悪くも日和ったというところになります。
これは誰にでもありえる話で確固たる一貫性をもつのは簡単ではありません。ある種サークル的なノリもあったり、一方で大学生がボランティアという社会的意義でカバーされる面もあり、なかなか「これ」という感覚を掴むのが難しかったんだろうなというのが伝わってきます。
最後には、法人格も冷静に考えるべきだったし、資金やビジネスについては自分で稼ぐなど別の視点があったほうが良かったと述べています。
新しいマナビーに
スペルは違いますが、名前はマナビーとして生まれ変わったようです。中高生向け勉強動画、8000本を完全無料で……新サイト「MANAVIE」の勝算 (1/3)に詳しいです。運営者は花房さんとは別の方のようで、関係がありません。
新しいマナビーは、動画講義の質を上げたのが大きなポイントのようですね。別の課外授業動画については視野を広げたりするキッカケを作るようです。
ビジネスとしては広告収益のようで、どちらかといえばオーシャナイズ(共同運営する会社)の顧客ターゲットを低年齢化するというところから、オーシャナイズモデルの得意とするところかなと感じました。タダコピなどで有名ですね。
この新しいマナビー自体は今回のテーマではないですが、失敗したサービスが生まれ変わるというのはこれもまた新しく、アイデアのリサイクル感は嫌いじゃないですね。リサイクルピボット(造語)という感じも受けます。
追記
2017年7月にオープンしたMANAVIEは、以下のように2021年5月に閉鎖して、連携していたターンナップと合流したようです。
2021年5月MANAVIEは閉鎖し、無料学習サイト「ターンナップ」と合流する運びとなりました。ターンナップは2021年内にリニューアル予定で、MANAVIEで活躍していた講師達も再登場予定です。
http://manavie.jp/より引用
教育はビジネスと交わりづらい
教育って非常にお金を生みだしづらいなと思っています。ちなみにそれをビジネス化する教育ビジネスは何か無理な点というか「ビジネス」というものが一体化しなかったり、ズレてしまったりしがちです。
もちろん、教育=お金になりづらい=価値がないなんて全く思ってなくて必要です。むしろ、非営利的なことって教育的なことや教育そのものにあって、例えば家族などでは子育てがありますし、会社では研修等の人材教育があります。義務教育もそうです。民間で塾や専門学校などはもちろんありますが、多くは自分でお金を払う学習よりも、教育というと学習者と支払い者が異なることが多いのかなと思うわけです。
教育=非営利的=社会的意義というのが僕は強いと思っていて、だからこそ教育でお金を取るというと批判されがちです。でも学校の先生は税金が投下されているわけで、公務員なわけですね。私立は違うわけですが。一方で学習塾は子どもでなく親からお金を取る。花房さんは予備校などに象徴される受験ビジネスを変えようと思ったと思いますが、貧困ビジネスではないですが、予備校に行けるお金がある家庭はいけるし、お金がない人は行けない。
それって塾に行けないなら学習が出来ないのはおかしいのではないか、ではやろうというのがシンプルな理由になるわけです。ビジネスという、お金を稼ぐことがここで不可欠なのは、結局非営利団体運営において寄付や補助金や会費などでは辛いんですね。これらは王道ですが、一方で知名度が一定あるとか広げるまでは踏ん張る必要があります。逆に言えば踏ん張って広がらないなら、寄付者は知らないから寄付できない、広がってないから寄付しないみたいな悪循環になります。
そういう非営利アクセルを踏むのもありだけど、一方でビジネスアクセルもありです。もっとも非営利とは収益事業なしではないので収益を上げていいのですが、このあたりは耳タコになるのでスルーするとして、教育ビジネスをすればビジネスをしていると叩かれるし、非営利でやればボランティアだと叩かれる(笑)そこは適度にスルーしていくことに結果的になりそうです。
一方でそういうことは行政がやるべきというのは最もな意見なのですが、これって結構問いかけとしては意味がなく、既に行政的には教育モデルがあるわけで、それが単に対応出来てないなら新モデルやあり方を誰かが作らないと生まれない。そういう意味で、manaveeがチャレンジしたことで、仮にスタディサプリとかが生まれたりまたはその素地を作ったというならば大いに意味のある活動だったといえるわけです。
おわりに
僕自身は今回のmanaveeを調べていくうちに、花房さんという人が何を考えていたのか、とくに公式の反省点と振り返りにおいて他の部分はどうだったか。そのあたりを知りたいなと思いました。
2017年3月にクローズということで、今後何をされるか、またチャレンジするということでこういう時こそチャレンジに失敗したとしても再度やれる、またはどんどん失敗して学んでいこう。そういう場や環境が大事だなと感じました。
最近僕の中では、何か一点でも際立つもの、または際立ってなくても特徴的なところがあればそこを完遂するだけでも普通はできないよねと感じるようにとくになっています。今までもわりと長所や良いところを見る方だと思っていましたが、より緩和されたというか(笑)そういう感じです。
花房さんがビジネス的視点があまりなかったというところが悪いということもなく、そもそもメディアで取り上げられたり話題を作ったのは良かったし成功だったともいえます。そこまでさえやり切れる人は少ないため、ぜひ今後の活躍を影で応援しつつ、ひとまず著書を読んで理解を深めてみたいと思います。
教育とビジネスの関係はそのバランスでアウトプットが全然違ってくる感じもしています。今後も見ていきたい業界ですね。
筆者プロフィール

- 「シゴクリ」運営者。アイデアの力でお客様に貢献するゼロイチ大好きアイデアマン。ビジネスアイデア相談実績等は200超を超える。好きな言葉は三方良し。詳しい自己紹介、仕事実績も合わせてご覧ください。お仕事メニューやお問い合わせはお気軽にどうぞ。
最新の投稿
 アイデアネタ2024年7月26日思い出はデジタル化はできないが、思い出のきっかけは常に残せるのかも。
アイデアネタ2024年7月26日思い出はデジタル化はできないが、思い出のきっかけは常に残せるのかも。 アイデアネタ2024年7月25日るるぶの豆本化に学ぶ。小さくしてみたら面白いかも。
アイデアネタ2024年7月25日るるぶの豆本化に学ぶ。小さくしてみたら面白いかも。 思考・考え方・メモ2024年7月25日キャリアモデル開発士認定証頂きました。
思考・考え方・メモ2024年7月25日キャリアモデル開発士認定証頂きました。 思考・考え方・メモ2024年7月25日シゴクリラジオゲスト回。キャリアモデル開発の長沼さんから刺激をもらいました!
思考・考え方・メモ2024年7月25日シゴクリラジオゲスト回。キャリアモデル開発の長沼さんから刺激をもらいました!