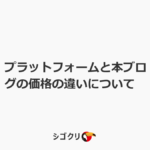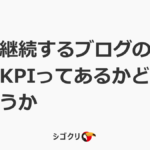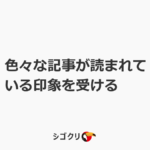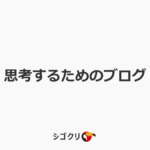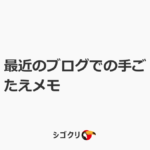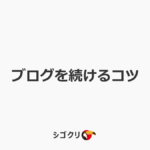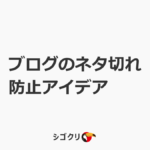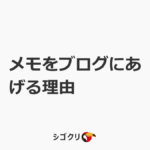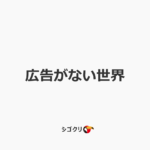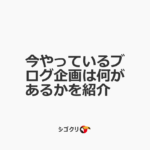ブログ600記事に。軽く振り返り。

今回はブログ運営ネタです。
このネタはわりと珍しく、確かしばらくブログ運営ネタをあげてこなかったからです。確かアナリティクスコードが二重にあって倍アクセスがあったと空喜びしていたのが懐かしいです(遠い目
今回は、600記事というところでこの数字自体に深い意味はないのですが、振り返るという意味では良いきっかけなので見ていきたいと思います。
目次
今までの振り返り
そこまでないんですが、
300記事は、開始1年で累計記事300突破。ブログ始める方向けに贈る、ブログを続ける7つのコツで書きました。テーマ、ターゲット、思い、ゴール、メリット、100記事はやろうぜということを偉そうに書いています(笑)
500記事は、ブログ500記事達成から考えるブログを継続するコツで書きました。そこでは、ネタ探しを常時しろ、伝えたいイメージを言語化しろ、外気にせず、モチベ維持のために運営記録をつけろ、軸ができたらいける。みたいなことを偉そうに書いています。
こう見ると視点も若干変わってきたんだなと分かります。
そして、600記事自体を考えると、明らかに1年で300、その後1年で200、そして、8ヶ月で100ということで、記事更新ペース自体は落ちていることが分かります。
ハイペースでガンガンというのは辛いので、このあたりはこれでいいかなって感じですね。
600記事を達成して思うこと
1.アクセスを追う欲が減ってきた気がする
消えたわけではないんですが、PVなどアクセス数を追うことに対して「欲」が消えていきます。溶けていくというのが正確でしょうか。とはいえ、無欲で0でもいいというとそれは違うので。ただ、これも一定のアクセスが安定してなければ言えないので、そういう意味ではこれからブログを始める人には「意味がない」のですが、なんでもやると見え方が変わっていくイメージが伝われば嬉しいです。
そんな形で、ブログ運営も前は毎月振り返りをしていたのですが、あんまり途中から機能しなくなったなあと思っています。
例えば、このコンテンツ入れたいと思ったり、企画したりしても、結構ブログ時間の中でどこまでやれるかっとなるわけです。つまり、課題は分かっていても着手できないとかかなりあった。となれば、それはあえていうよりも、日々の中で着手したものを出して行くほうがいい。そんな感じです。
例えば、塩漬けになってるっぽい企画もタスク的には残っているものが多く(読者的にいえば、あの企画最近ないよねって感じです。もちろんリピーターさんしか分からない)、それらはいつやるのって感じになっています。もちろんやる気がないわけではないが、やれないなら・・・という話になってきて。
これらを運営記事としてあげていくことで見えるものがあったり、ちゃんとやらんとかんなと思えたりとか。そういうことを期待していたのですがそこまでワークしてないなと。
あとは、マーケティング的な意味で何が記事として受けるかとかの分析、キーワードとか、記事内容とか、他にも最近やってないですが、コピーされた文章はなにかとかです。
具体的にいえば、ザ・プロフィット企画は5本で終わってます(笑)が、実は本自体は何度も読んでいるのでアウトプットできてないだけなんですよね。このあたり個人的にはやりたい企画なので手応えもあるのでもっとやっていく「つもり」です(笑)期待せずどうぞ。
2.軸とか偉そうにいってるけど未だにブレブレ
軸という意味でテーマ性は変わっていません。アイデアをどう仕事にしていく、起業っていわなくてもシゴトですよね。そういった試みをココナラだったり、色々なプラットフォームとして、ランサーズなどもですが、試しつつどうなっていくかを検証してきました。本ブログからの問い合わせでシゴトになるかとかも含めつつ。
そういう意味でキーワードとしては、「アイデア」「ビジネスアイデア」「仕事の作り方」「企画の考え方」となっていって、ターゲットはそういうことを学びたい人、またはアイデアを探している人となります。
実際に手応えがある記事が、最近はアイデア応募まとめ記事、アイデアネタ記事+アイデア売れるか、あとはIT系のTIPSとなっていて、この手応えとテーマは合致していると言えます。
欲をいえば、もちっとアイデア系によっていると思っていて、これは以前も書いたんですが、そこまで「アイデア」というもので染めてないんですよね。理由はアイデアって結局いたるところにあって、「アイデア」と書かれてなくても「アイデア」だねというのが多い。例えば、僕のコラムなんて読みたくなくても、「そういう視点があったのね」と気づけばそれで「アイデア」を伝えたことになります。ここらへんが面白いところでもありますね。
ブレブレとまではなりませんが、このブログ一本で食えるとかは当然無理ですし、それを目指すのかはかなり微妙でただ、営業ツールとして、または自分を尖らせていく、自分のメディアとしてワークしていくためにまだまだ検証が足りてない。そういう意味では達成感はそこまでないというか、ないですね。
とはいえ、じゃあ記事数を増やしまくってとか、なんか短期的にどうこうする話でもないなあというところです。
3.ネタが消えることはない
もちろん自分がネタを探してこれ書いてみたい、調べたい、もっと深めたい、この視点同じこと思っている人いそう、困ったら共有するみたいな感覚は変わりません。
それでネタが見つからないのでは?という心配をする方もいると思うんですが、ネタはあります。ネタが見つからないというのはかなり致命的ですが、あまり起き得ないことです。
理由としては、
- 好奇心とか人格的な性格、環境として病気で入院とか、何か環境が激変しない限り、恒常性として「ネタを見続ける」から
- 日々の情報に触れた時に出てくるリアクション、注意や気になるなどの感覚がすぐ消えることがそもそもないから
- 極端にいえばアウトプットする過程でも生まれるし、人と話しても生まれるし、人として生きているなら多分消えない
- 仮に消えるなら、それは自身の興味がどうにかしちゃった時とかに限られる。これは起こりづらい
というところです。
要は、ブログを書くからアイデアマンであるとかそういうことではなく、そもそもアイデアを出したいし、アイデアで貢献したいからこそたまたまブログでアウトプットするという意味合いです。
本質はアイデアを出していくことであり、ブログは手段です。ブログは手段ですが、手段を通してコミュニケーションが生まれるのでついつい見える「ブログ」を重視しがちなんですよね。なんでもそうですけど、水面下のものはみえないですからね。
そういう意味でネタ自体は変わりますが、ネタが消えることはないでしょう。そこは続けて見えてきたり、数年続いて数百記事書けるならインストールできたし出来るといっていいんじゃないでしょうかね。
4.飽きるかどうか。飽きなかった。
これについては飽きてないですね。というか、書くのが好きだからというのは大きいです。メモもしますし、言葉にするのも好きだからです。
これらがない人にとっては、ブログは異種格闘技っぽくて大変かもしれません。一方で書くと一定数いけるという何か好き、趣味、やってきたことがあるならわりといけそうです。構えると失敗しがちというかうまくいかないのですが、そこも構えをガチガチにせず、やっていくうちにという「気楽」さを入れると良さそうですね。まあ言うは易く行うは難しなんですけどね。
飽きる時って大体僕はすぐ飽きます。だからこそ、自分がコアで軸としてある部分として、書くこと、文章、言葉というのは外せないのだなと思います。書いてないと不調になるというか、もちろん書いているからその文章価値が常にあるということでもなく、自分のメンテナンスという意味でも、それは「自己を満足させる意味で」は成り立つので、最悪読者がいなくてもって感じになるんですね。
このあたり色々議論?というか意見はありそうです。自己満足で書くなパターンですけど、それなら見なければいいし、見ないのがインターネットって感じがします。もちろん、反社会的なのは置いておいて。多くはそのレベルでなく、単にいちゃもんであったり、難癖つけてどうかなので、そのレベルであれば相手にしないのがいいでしょう。
そういうことを置いておいて、飽きないし、続けられるのは、ブログ自体を使って自分の学びになる、成長にもなる、そしてそれらを使ってコミュニケーションをしていける、武器とか道具になってきたからでしょう。それについて結果や成功したことをことさらこれということを言っているわけでないですが(例えば初対面の人に何かブログを書いていてとか言わない)、とはいえ形になって見えてくるものがあれば色々言えるわけですからね。そこは焦らず積んでいくしかないですね。
結果的に飽きなかったし、やはり飽きなかったから続けられるよねというところが率直な気分ですね。
5.楽しもうとして書くってなかなかむずい
4にもつながりますが、飽きてしまったりすれば無理に楽しもうとするし、辛いとか面白くないのに楽しもうとするとなんだかというのも実際あるでしょう。
書きたいものがないのに無理して書けばそれは自分も辛いですが、読む方も面白くないです。筆が乗るという感じでいえば、タイプが進むといえばいいのでしょうか。それが出来るなら楽しんでいるし、楽しんでいない場合はそれらが全然出てきません。書いては消してみたいなことをしている人はそういう状況かもしれません(笑)
もちろん楽しむというのは大事なので、楽しもうとしていくわけだし、面白くやろうとするわけです。発散的に書いていってあとからどうかとすればいいけれど、収束的に書くと「箇条書き」の連続で、その接着剤や行間が冷たいので、人間味がなくて本当にあなたが書いたのかってくらい面白くないし、それがないからこそ微妙な気分になるかもしれません。お互いに。
禅っぽいですが、楽しもうとすれば楽しめない。つまらないならつまらない。しかし、楽しもうとつまらないの間は、何かニュートラルな何かがあるのかどうか。多分なくて、本当に自分の気持ちをガツンとぶつけるか、どこを面白がっているかが見えるとそこに焦点をあてて、そこで高めていく感じです。
というのは、すでに書いていて、
前の記事で、
1.日常で気になったことをメモする、またはちゃんと感じる(五感を高める)
(ブログ500記事達成から考えるブログを継続するコツから引用)
なんて書いています。つまり最初は感覚であり、五感が死んでいたら駄目ですが、それを働かせることです。耳で聴いてるのか、目で観ているのか、鼻で嗅いでいるのか・・・。それらから色々なことを捉えていく、まさに観察が問われるってことですね。
これらが楽しいかはあまり心配しなくてもよくて、観察できるってことは一定の楽しさや興味がないと辛いです。または観察したところで何かが見えるかどうかです。その変化があれば、花も観察できます。花を見るだけでなく、観察です。色はどうか、形はどうか、なぜしぼんでいるのか、なぜ成長が遅いのか。これだけでもネタになりますよね。本当に理科の観察と同様です。
物事が変化することが多い中で、一点だけ観てもこれだけあるわけです。ほらここまでいえば、なんかネタあるし、書けそうだなあって思えませんか?
自分に正直に生きる
自分が考えたことを話す、伝える友人やパートナーがいればそれで満たされるので十分だと言うのもありです。実際に親友としては話す回数は激減しても話す内容はそれほど変わらずです。興味のベクトルが変わらないなら続くし、変わってもなるほどなあということで楽しめるわけですから。
自分に正直とは人に対して嘘でもいいということでなく、なるべく素直に生きたほうが摩擦も無駄なことも起きづらいです。もちろん、インターネットで拡散されてメッセージが曖昧になって切り取られ加工されたらやりたい放題ですが、それって悪意でしかないのでスルーするとしても、本質的に見える人が減ることはなさそうです。それほど人は馬鹿じゃないってことです。
むしろ、馬鹿じゃないからこそ、頭を使っていくと。そうなると人は寡黙になるし、あえて言っていくことも「一定の思考の上で」となりますから、深みが出てくるわけですね。
それはいいとして、自分に素直であれば、ストレスはないですし、人に対してもフラットに構えられます。失うものがないのは強みであり、また抱えるものが多いと守らなければいけないというリスクも出てきます。ノマドを勧めているわけでなく。
だからこそ処世術としては、ブログでなくてもいいんです。SNSでこっそりでもいいし、心理的安全があるような場所、働くところでも、ほっと出来るコンビニでもいいし、話せるカフェでも、心置けない仲間でもいいし。そのあたりどれってことはないんですが、それだけがあればわりと人生が動くならやっぱきちっと確保して自分のために使っていくというか、キープすべきだなと思います。
そういうことにケチをつける人は一定数必ずいますが、自分でない人の人生にケチをつけてもその人が何かするわけではないのでスルーでしかないですね。自分は自分のために自分のメンテナンスのために、何かやる。それって前向きで素晴らしい人生ですからね。
プロという意識
いくつか600記事達成ということでググったらブロガーな皆さんが記事を書いていたのでそこらへんを共有したいと思います。
ブログを半年で600記事を達成した今、思うことでは、半年で600と鬼のようなペースで真似できません。その点はおいておいて、プロ意識だなと感じたのは、ブログを書く時間がないので、そのためにポメラとノートPCを使いスキマ時間でやったという話が面白いです。
このプロ意識とは、別にプロ=その仕事で食える、ということという意味でないです。昔書いた記憶がありますが、アマチュア意識のプロと、プロ意識のアマチュアなら、後者の方が応援したいし面白いと感じるからです。俗にこれらの人はセミプロといわれている気がします。前者のプロは確かにプロだけどなというところです。もちろんプロになるには一定の時間投下とそれなりの学びと興味がなければできないですが、そこはおいておいて、ここでいいたいのはプロ意識です。
仮にブログを書くというのがぬるい目標であればここまでするのか?と思うわけです。実際にスキマ時間があれば他のことをしたいならそれは「ブログを書かなくてもいい」ことになります。目標を達成するために何を捨てられるかでもあるし、限られた制約で何をするかということでもあります。こういうのって男性の方が向いている印象がありますけど、それこそが意識であり、プロ意識です。
つまり、ブログ初心者であれば「隙間時間とか無理。そこまでしてやりたくない。そこまでやるの!」と思うのですが、実は世界は逆です。「そういう工夫をしてやりたい何かがないと続けられないし、そういう工夫がないとまず最初ができない」です。もちろんこれはタフネスやマッチョさがあればいいとか、気合根性の世界ではないです。計画を立てる時に、自分の6割程度の動きでやれるほうが適切ですから。ただし、「工夫もしたくないし、頭も使いたくないし、楽にやりたい」はタダのサボりですから、それと「楽して何かやる」という知恵行動と、ただのサボり行動かを分けているだけですね。
労せず何もせず得られるものほど何もないし、価値もないというだけの話ですね。
ブログ記事数600記事到達!これまでの当ブログ成長過程をまとめたよ!では、淡々と書いていくというところで、何か劇的な変化があったわけではないというところです。全くそのとおりですね。こちらも全く同じ感じです(笑)
ブログを600記事書き続けてわかったこと。では、600記事書いて、ブログの難しさがわかったという話があります。ライフスタイルが変わり書いていくことの難しさがそのまま出ているということです。確かに自分のライフスタイルが変われば本ブログも意識が変わります。例えば意味がない思考実験ですが、10億円が転がり込んできたらそっとブログは放置するわけです(笑)仕事も変われば多分「何アイデア?馬鹿いってんじゃねえ」みたいに人格が変わってしまうかもしれません。
700記事までいけるのかってことが気になったので最新のブログ論を見ると、670記事を書いたぼくが今だから思うブログ運営のひとりごと。では、3年続けられる人はあまりいないということが書かれています。本ブログも、2016年からなので、あっという間に3年になりそうですねえ。今の所ブログを辞めるということを考えたことはありませんね。とはいえ無理してやることでもないので、続けられるペースと付き合い方を常に模索しつつですな。
ブログ600記事達成して今見える事、ブログは人生が豊かになるツールでは、実際に観てみる、それこそ観察する、体験するということを意識的にやることで、書くことにつながるという話があります。その通りだなと思います。確かに情報が多い中で、ではそこにいったのかは価値となりますし、全員がそこにいけるわけではないです。SNSはその場で発信出来るけれど、一方でそのソース自体は簡単にフェイクもできるため最近はSNSのあるきかたができてないと辛いことになりそうです。全て0か1で片付けられるわけではないですけど。
ブログの記事数とアクセス数|5万PVまでの道では、500から700記事までが凪状態で、800から900でステップ、1000記事までいうと、ぐっとあがった感じとなっています。5万PVが1,000記事でいけるという目安になりますが、中小企業向けの経営戦略というビジネスコンテンツなので、ターゲットが絞られるため、一般の生活ネタとは異なる形ですね。グッジョブですね。
単に記事数だけでは分かりませんが、一定の参考になりそうです。とはいえ1日3-5記事をあげたりはできないですけどね。
いくつかの伸びるまで凪状態が続くのは覚えておいて損はなさそうです。プラトー状態と呼ばれるはずで、学習でも一定の期間全然覚えているし学んでいるけど伸びない時期があります。スランプと思いがちですが、色々そこで踏ん張っていると次が見えます。踏ん張るってのはこういう時に粘る時に使うべきでそれ以外はわりと筋が悪い忍耐です。
ただ、これらの我慢や忍耐が今はそうすべきかどうかが分からないし、あとからしか言えないのでなんともなんですよね(笑)
おわりに
ざっと振り返ってみましたが、自分を信じて書いていくしかないですね。自分の大事なパートナーとしても頼れる相棒ですね、そんな形でふんばっていこうと思います。
そこまで力まず次は700,800,1000というところをいきたいと思います。
筆者プロフィール

- 「シゴクリ」運営者。アイデアの力でお客様に貢献するゼロイチ大好きアイデアマン。ビジネスアイデア相談実績等は200超を超える。好きな言葉は三方良し。詳しい自己紹介、仕事実績も合わせてご覧ください。お仕事メニューやお問い合わせはお気軽にどうぞ。
最新の投稿
 アイデアネタ2024年7月26日思い出はデジタル化はできないが、思い出のきっかけは常に残せるのかも。
アイデアネタ2024年7月26日思い出はデジタル化はできないが、思い出のきっかけは常に残せるのかも。 アイデアネタ2024年7月25日るるぶの豆本化に学ぶ。小さくしてみたら面白いかも。
アイデアネタ2024年7月25日るるぶの豆本化に学ぶ。小さくしてみたら面白いかも。 思考・考え方・メモ2024年7月25日キャリアモデル開発士認定証頂きました。
思考・考え方・メモ2024年7月25日キャリアモデル開発士認定証頂きました。 思考・考え方・メモ2024年7月25日シゴクリラジオゲスト回。キャリアモデル開発の長沼さんから刺激をもらいました!
思考・考え方・メモ2024年7月25日シゴクリラジオゲスト回。キャリアモデル開発の長沼さんから刺激をもらいました!