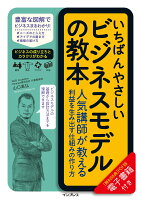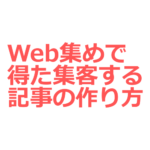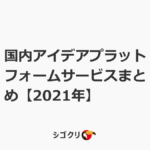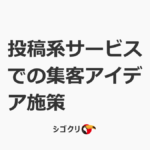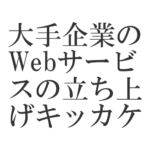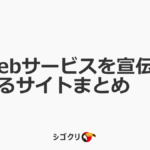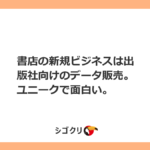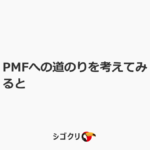最初の顧客など初期ユーザーの獲得方法まとめ
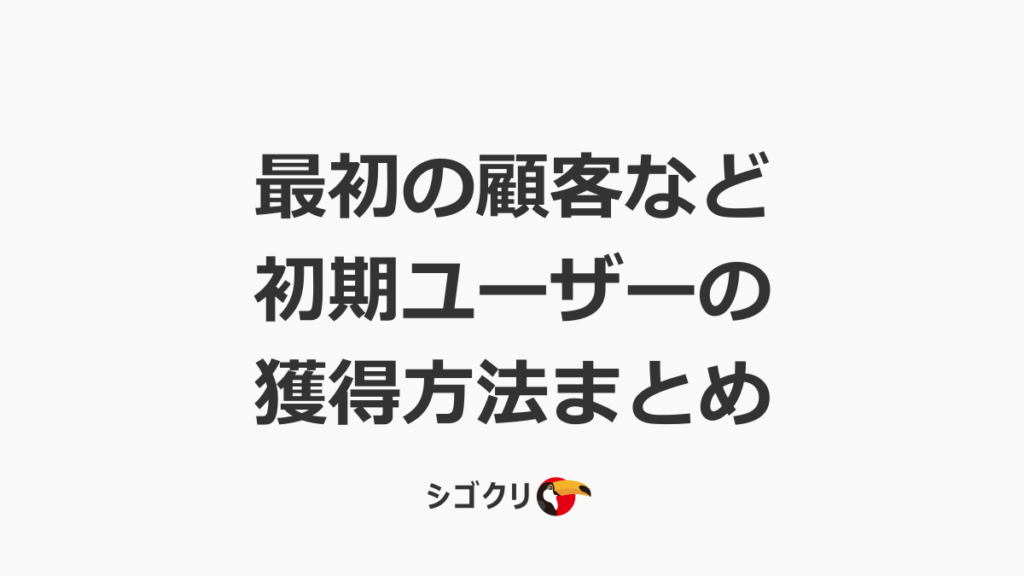
Webサービスでの運用アドバイスとなるとこのどうユーザを獲得するか。まあ普通に課題となるわけです。そういう時に、他はどうやったか?を知ることは大事です。
もちろんこれをそのまま使えるとか、それをやれば正解とかはなくて、そうでなく選択肢としたり、ヒントに使うということですね。
スタートアップ、スモールビジネスから様々ですが、結局使えそうならそれをヒントにやることがベターなのでどんどん活用してもらえれば嬉しいです。当然それをやった人が素晴らしいので、そこはリスペクトしつつ。
ユーザ獲得の考え方
まず軽い前提です。どこかに自分のサービスを使いたい人がいてそれに出会えてないとかって悪くないと思います。なのですが、そのユーザはどこにいますか?と真の意味で問いかけたり聞いている時点で終わっている感じがします。終わっているとは、詰んだということで、そうでなく、そういうユーザに自分は近いからこういう人じゃないかとか、見つけていくアクションとか、そういうアイデアがなかったり、アイデアを探そうとしなければ結構辛いということですね。
あと、初期ユーザでいえば、最初の1名も、100名くらいまではざっくり初期サービスとか、初期のリリース直後と考えると、スタートアップとスモールビジネスは違うといえど、結局グロースなど急成長であったり、成長モード全開とは違う気がします。つまり、広告を出してどうとかは早いし、価値の検証って意味でサービスと向き合って価値がなにか、ユーザとのコミュニケーションに全開(話すということも含めて)にすべきというところです。
参考になった記事など
以下参考にしたものです。ありがとうございます!ユーザ獲得事例は、記事内に参照元を上げていますので、考え方や見方などですね。
「リーン・スタートアップが機能しないワケ」というブログの誤解について
人気C向けアプリはいかにして初期ユーザー1000人を獲得したのか?
【インスタ、エアビー、Slack等】人気サービスの初期ユーザー獲得方法
泥臭いというか、泥臭さですよね。それできるかって別に気合いとか根性でなくて、そのサービスを届けたいとか、ユーザの課題を解決したいかと向き合っているかってだけだと思います。そのレベルが低いなら面倒になって動かないです。動けないというのが正しいですね。泥臭いことをしないと駄目というか、泥臭さしかなくなるというのがこの初期ユーザ獲得という理解を僕はしています。泥臭いのやだからというのもありですが、それでユーザに向き合っているなら全然OKです。でも、結果的にお金もリソースもないなら、出来ることが結果的に「泥臭い」という感じですかね。伝わりますか?
初期サービス・ブランドのユーザー獲得における基本戦略
つまり、一言でいえば、ターゲットユーザーにあって話を聞く、聞きまくる。その上で手当り次第でアイデアを試すってことになりますが、その通りだと僕も思います。手当り次第でアイデアを試すだけだと、ターゲット見えなくなるので、そこはターゲットから聞きつつ担保して、アイデアを試すってことがいいかと。
これも開発して出来なかったとか罠にはまったりとか、やろうとしてやれなかったとか、なぜかアイデアは大事ですけど、アイデアを試すことが楽しくなってユーザを放置してしまったりとか。色々あるんでしょうけど、聞きまくることで損はないです。同時にユーザの言うことが正しいとかは結構難しい話で、嘘もあるわけで、あとはどうバランスを取るかでしょうか。課題がないのに課題があるという嘘を言うことはなくても、感情の嘘だったり、表現誤解だったり、これらはもう経験していくしかなわからないですよね。いやしていても分からない世界なので、聞いて聞いて、でその上でサービスを提示していく感じですかね。
個人開発で最初の100人のユーザを獲得するには
この記事も面白くて、友達の輪で広げるか、インフルエンサーか、自分たちでやるかというところが手段や選択肢で挙げられています。どれも正解というか駄目とかはないのですが、どれをやるかって話ですよね。例えば、友人知人を誘ってそれらがコアになって広がっていくとかってありがちですけどそれも出来る仕組みを考えているかですよね。口コミになれ!って祈っても仕方がないので、その知り合いらが価値を感じるレベルではないと無理なわけですしね。
インフルエンサーが紹介するのもありですがないならされるまで粘るとかですし、その人が適切にシェアしてくれるか。お金を出してとかは嫌われるというかPRならありですがそこまでやれるのかとか。
この記事では自分たちで内製するということでコンテンツを作るってことですが、これは個人開発ならやりやすい手段ではないかなと思います。当然それをやれる気力がないなら駄目ですけどね。
「12回の事業転換」世の中の課題見つけられずに SmartHR・宮田昇始社長
そこからはめちゃくちゃにピボットをしました。まず「(こんな課題があるのではないかという)課題の仮説」を立てて、それを解決できそうなサービスのプロトタイプを作ります。それについて5〜10人にくらいにヒアリングして、課題としてアリかナシかという判断を1週間でやる――こんなことを2カ月間くらいずっと繰り返していました。
「12回の事業転換」世の中の課題見つけられずに SmartHR・宮田昇始社長
見付けた課題や仮説が刺さるかどうかの判断はおいておいて、ここでも確率は1割くらいなので、自分がいけるのでは?というところもそんな確率感かもなあと感じましたね。ピボット12回くらいまでは色々変えて探っていきたいなあと一つの目安になると感じました。もっともスタートアップとして何かやろうという気持ちはないので、そこは補正しつつ。にしても、いい記事ですね!
サービス毎のユーザ獲得事例
規模やターゲットやジャンルなどごっちゃです。意図はそれぞれに最適な何かがあるということと、それぞれ「泥臭い」ので、そこを学びつつヒントにするという狙いだからです。
Bizer
BizerTeamは、
- Bizer顧客を1500社から2割に大手企業を対象にして、サンカクを利用して意見をヒアリング
- 事前登録をしてもらいつつ、セミナーで100社で20社程度が契約
- 初期50社は知り合い。Facebookメッセージを送る。
Bizerは、
- ピッチイベント参加
- Web広告など広告は伸びるが一定ペース
- 類似サービスで相互送客。Bizerで会社設立したら、freeeを使ってもらうなど
- Coffee Meetingやタイムチケットで、出品して起業相談を受けて、最後にちょっと営業。半分の人が買ってくれる。
参照元:Bizerは最初の100社の顧客をどう開拓したのか?
BizerTeamはBizerがあってこそなので、肝心のBizerはどうだったかというところで、面白いのは、相互送客とか、タイムチケットで起業相談して最後に営業とかってやり方ですね。これも明らかにそれでやると問題が起きそうですが、基本サービスをやってご興味あればというところなのでまあ問題になることはないですよね。賢いやり方です。
自分もやろうかなと思ったりしました(笑)相互送客も面白いアイデアですよね。つまりサービスを手動連携みたいにして使っていって相互に効果を出すということですよね。面白いですよね。
ツイ消し職人
- リリース後、平均20人/月の成長。課金買い切りで700円
- Twitter広告などターゲットがTwitterユーザのため最も効率的と思われる
- 友人に知らせる、PRなどやれそうなことは一通りやった
- リリース11ヶ月後の今でも購入者600人と順調に成長
参照元:有料のWebサービスをリリースするまでに取り組んだこと・知見をまとめました【個人開発】
個人開発の知見が参考になりますね。ツール系でターゲットも明確、自身の痛みや使いたいところもありターゲットに刺さったというところといえそうです。とはいえこれやりきるのが難しく、素晴らしいなあと思います。
クラウドワークス
サービスリースの3ヵ月ぐらい前から、東京で有名なエンジニア、関西で有名なアプリ開発者などに声を掛け、30人ぐらいの顔写真を借りて掲載
「”課題を自分ごと”として解決していけるかが”やり抜く力”の源泉」クラウドワークス代表取締役社長 CEO 吉田氏にインタビュー
この話はよく聞いたことがあるのですが、なるほど戦略的だと感じますね。初動が大事というところで非常に参考になりますね。
- Twitterでコミュニケーション、小さめオフ会、ミートアップに協賛やそこでしゃべる
- 30人に協力してもらうことで、事前登録数は1300人に
- その1300人のリストをもって、クライアント30社を集める。両者が集まったタイミングで公開
初動を大事にというのもありますが、地味にコミュニケーションとオフ会で話す、プレゼンするを通してコアな協力者=ユーザを得ていく作戦は強力です。これが出来ればある程度の成長か、またはある程度いけるのかもしれないですね。
顔写真を借りるのも秀逸でそこまでのコミットや協力や信頼を当然できているのは大きいですよね。
参照元:「”課題を自分ごと”として解決していけるかが”やり抜く力”の源泉」クラウドワークス代表取締役社長 CEO 吉田氏にインタビュー
タイミー
小川さんの、常に本質を捉える思考は、実際の事業計画や経営手法にも表れている。タイミーのアプリ開発を始めたのは、リリースのわずか2カ月前。それまでは大学の友人ら300人ほどにLINE@に登録してもらい、自分がクライアントから獲得した案件を流してマッチングを行うことで、ギリギリまでサービスの需要を仮説検証した。
「タイミー」学生起業家 事業を成功させるには「自分がそのモノやサービスを心から欲していること」 大学には先輩起業家と学生をつなぐ「器」を期待
- まず友人から巻き込んでそこでギリギリまで検証している
- 次のコメントでは、コンセプトさえ再現できれば他のシステムで代替でもOKという視点
友人に試してもらってギリギリまで検証しているのが素晴らしいですね。上のコメントの次では、「コンセプトさえ再現できれば」というところの、コンセプト検証をしっかりとやっているのがいいなあと。
300人の友人がいるかどうかよりも、3人でも最初そこから広げられるかですよね。結構熱がないとこれはできないんですよね。
参照元:「タイミー」学生起業家 事業を成功させるには「自分がそのモノやサービスを心から欲していること」 大学には先輩起業家と学生をつなぐ「器」を期待
食べログ
村上 まずは何もないところから始めたので、グルメ本を買ってきて調べてはデータを手で打ち込んでデータベースを作るところから始めました。最初は、やっと6000店ぐらいからサービスを始めたのですが、店側の情報も会員(店舗会員)になってもらって無料で掲載し、全国に70万店以上ある飲食店をほぼ網羅したいと増やしていった結果、毎年倍増する勢いで伸び、他のグルメサイトと比べても圧倒的に掲載している店の数が多くなりました。
【ポスト・デジタル革命の才人たち】 「食べログ」村上敦浩さんインタビュー(上):口コミの集積がビジネスになった理由
食べログの村上さんは「たった500人でこんな大きなサイトが成り立つのか」と驚き、同時に「500人なら自分でも集められる」と考えた。
「食べログ」開設当初の戦略/マーケティングトレース note100本ノック 1/100本目
実施したレビュアーの集客方法はシンプルで、友人に声をかけたり、めぼしいブログのコメント欄に書き込んだり、先行サイト(livedoor グルメやアスクユーなど)のメッセージ機能を使って勧誘を行ったことである。
- 最初にアナログでデータを打ち込んでデータベースを作る
- ライブドアグルメなど競合サイトでメッセージで勧誘し直接誘う
最初に地味にやるのが大事ということを痛感します。データベースを6000件打ち込むって結構手間なので、それをやる時点で熱量が高くないと、終わりそうです。100くらいまでなら誰でもできそうですが、1000を超えるとわりと問われそうですね。
その上で、他サイトに対してもそこからメッセージで勧誘していくということですね。
やはり500人でいけるなら自分でもやれると思ったり、そうならこうすればいいのでは?とアイデアが浮かんだ時に、まずはどこまで初期で固められるかというのがポイントとなりそうです。サービス開始のタイミングは難しいものの、コンセプトや価値が検証できる程度であればGOという理解です。
Webサービス集めました(自分)
自分の運営ネタです。自分で最初はサービス投稿していたというのは事実なので示しておきます。
運用2ヶ月目では100投稿中8割が自分という自作自演状態でしたが、今は全く自分では投稿はしていません。皆さんからの投稿で回っています。これはありがたいことです。
Webサービスを作る時の実際の企画書を見ながら、今までの運用と学んだことを振り返る
- リリース直後は過疎っぽくなるので自分でおすすめしたいサービスを投稿していた
- 100投稿で8割は自分で、2割のみがユーザ投稿。その比率をどんどん改善していって、最終的には月10-15件の投稿のみを審査する形にした
- 集客出来る記事として自身のサービスを含めた紹介記事をリリースした(https://readmaster.net/think-issue-memo/webatume-syukyaku-houhou/で説明)
僕のサービスで恐縮です。似たようなものもあると知りつつリリースしました。
捉え方は「競合がある=無理」でなく「競合がある=市場がある」という感覚を評価しました。これについては、多分見方が色々あって正解はないです。先の食べログでは競合としてライブドアグルメとかがあるところで諦めるのか、それともこれでいけるならこっちもやれると思うのか。その肌感が大分大事な気がします。僕の場合は、やれるというよりも、「ニーズはあるのだろうか」くらいでリリースした感じですね。
このサービスはシンプルなので、最初に宣伝できそうと思えれば良く、そのために投稿をする手間やハードルを下げれば良いとなります。そのために、僕はまずは自分で投稿すればいいのではと考えました。実際にここで自分がおすすめしたい、面白そうなサービスがないと詰みます。僕の場合はそういう面白いサービスを紹介したいというのもあったので、問題なく、むしろ楽しく出来ました。それを見たユーザーが他薦や自薦もぐちゃぐちゃでしたが勢いか見たところで評価してくれたのか、とくにお願いをするわけでもなかったはずですが、結構集まってきたという流れです。
あと実際に支えられているのは、ブログ経由の投稿です。当時で8割くらいまでそこから登録していたというデータがあるので、まとめ記事→使ってみるか→投稿するという流れは鉄板となっていたと、今もですが、言えそうです。「Webサービス 宣伝」とかやると、上のまとめ記事が出てくるので、そこをざっと使ってみるかという人は多いはずので、one of themということで含まれるってことですね。他者サービスを紹介しつつコメントして紹介するところはあまりなく、あっても自身でそれを客観的に見せるというと、多分結構やらないんですね。なぜなら客観性の担保が消えやすいのと、冷静に書けないからでしょう。多分持ち味は色々なサービスにあるはずで、そこを冷静に見て書くということはやってきたのでそこも使えたのではないかな?というところです。
自作自演がどうとかってあまり考えてしまう人は行動が遅くなりそうです。早ければいいということもないのですが、やりたいことがあって、熱があるならやるべきですし、これやりきれないなら多分やれないし形にならないです。それだけなんですが、これ別に経験値があってもなくても分かることで、あとは解像度やどう見極めるかとかってことですよね。
ココナラ
- 良い出品者を事前に集めた。
→最初の空気感が大事。そこで決められてしまうので。
→レベルが下がっていくことは簡単だが、レベルを上げるのは困難。よって最初の出品者のレベルが大事。
- β版を作ってユーザーに試してもらった
→7,8割は南氏含めた創業メンバー3人の友人。
→約1000人に一通一通メールを出して、400人がベータ版に登録。200人がサービス出品をしてくれた。
以上2点が大きなポイントだと言えそうです。
参照元:webサービスの作り方をココナラに学ぶ!立ち上げ時におさえたポイントとは?【schoo(スクー)】 新サービスはいかにして立ち上がるのか?
結果的に30代だと思われますが、ビジネスや人生経験がそこそこある人が、自分の出せるものを出してくれたので、出品者のクオリティが高くなったと言えそうです。これもクラウドワークスであったような初動、初期のユーザーで全て決まるという感覚と同様かなと思います。方向性が決まってしまうのでということですよね。
そこまでせずに後から改善していけばいいって思いたくなる気持ちは分かるんですが、ユーザーで決まる場合はユーザー自体の体験、ココナラでは出品ですよね、そこで決まっちゃうんですよね。サービスの価値を出し惜しみしてそこで得られないと次はないというか。これ別に何か仕事するときでも出し惜しみとかすると、まあなんか不遇に終わったり。難しいですけど、最初からフルスロットルでありたいですよね。
だからこそ、ココナラを真似たサービスって結構見ましたし、ココナラももちろん海外サービスとか見てたりするとは思うのですが(Fivverとかなんかあったような、忘れましたが)、似たようなスキルシェアサービスがあっても、結局勝てないですね。多くは消えていったか、僕は使わなくなった気がしています。
1000人の友人がいるかはおいておいて、そのための施策として、何かイベントをやるとか、応援してくれる人を作るとか、それって重要な気がします。そのために動けるかが超大事でして、それができないなら結構熱量が弱いということですよね。ちなみに、僕は起業で失敗していますがこんな熱量は当然なかったですよね(笑)
仮説検証のポイント
さらに仮説検証の細かい点も南さんが語っていました。
大きく2つあります。
1つ目は、
(中略)
マーケット上で実際に売り買いされうるサービスを80個ほど考え、それを持って100人にアンケートを取りました。「この中でどれが欲しいですか?それはなぜですか?」と。
そのアンケートの結果、回答が“バラけた”ことで1つめの仮説がクリアになりました。
合理的に見える事業はNG 仮説通りに行くビジネスプランの鉄則|ココナラ 南章行 #2
想定サービス商品をリストで出して聞いたわけですね。これで使いたいとか利用したいものがあるか。その結果がバラけたので「プラットフォーム」として束ねれば偏らずにいけるのではないかということが見え始めるというわけですね。
2つ目は、
具体的には無料の掲示板借りて、知り合いで何かしらのスキルを持ってそうな人たちをかき集め、「××ができます。相談にのります」と書いてもらったものをリスト化し、そのURLを別の人に送って「この中で相談したいものある?」と聞いて回りました。
そして相談したいものがあった場合、実際に掲示板の中でスキルを持った人と相談したい人同士でやりとりしてもらい、その行為に対してお金を払いたいと思うかどうか検証しました。これが2〜3週目にやったことです。
同上より
実際にマッチングして手動でやりとりなのかまではわからないですが、やりとりしてもらって検証すると。「お金を払いたい」ところを確認するというのもいいですね。
記事には3つ目として相談の価値や自分たちのケイパビリティなどもありますが、気になる人は読んでみるといいかと思います。
実際にサービスリリース前に価値検証をしっかりやるということでとても参考になるかと思います。
Quora
Quoraは運営陣がアカウントを作成し、各自のプロフィール上でほかのユーザーからの質問に回答、または逆に質問することで「Q&A」を増加させました。redditも同様に運営陣がアカウントを作成してスレッドを立てていたのですが、さらにredditの運営陣はフェイクアカウントを作成し、運営陣が公開したリンクを多くのユーザーが共有しているように見せかけたとのこと。つまり「自作自演」を行っていたわけですが、redditの共同創始者であるスティーブ・ハフマン氏によると、フロントページに「自作自演スレッド」を出す必要がなくなるまでに数カ月かかったことを明かしています。
また、当時のredditには特定のジャンルをまとめたコミュニティを指す「subreddits」がなく、全てのジャンルの投稿が同じ場所で行われており、Quoraはテクノロジーのジャンルに絞ってQ&Aを増やすことに専念していました。双方とも1カ所にユーザーが集中することになったため、ジャンルごとにユーザーがバラバラになることなく、コミュニティがにぎわっているように感じられたのもユーザー増加の一因となったそうです。
Dropbox・Airbnb・reddit・Tinderなどは初期のユーザーをどうやって獲得したのか?
自分たちで投稿して質問しあったということですよね。数ヶ月かかったというところなので、結構ゴリゴリやりあったことが分かります。個人開発ならコミット次第ですが僕でも半年くらいやって手応えないなら諦める感じですね。スタートアップならどうかは分からないので、違うのだとは思いつつも。
この自分で投稿するやり方は地味ですが色々と検証もできるし、メンテナンスにもなるし、ユーザーの変化にも対応できる(例えば登録したらコメントするとか)のでいいやり方ですよね。
上の記述はredditは数ヶ月とあるのでQuoraがどれくらいやっていたかはちょっと分からないです。原文を見ても分からずでしたので、Quoraがどこまで自作自演していたかは不明ですね。でもまあ、いずれにせよ投稿系サービスのredditも同じことをしていたということで、知見となりそうです。
参照元:Dropbox・Airbnb・reddit・Tinderなどは初期のユーザーをどうやって獲得したのか?
Inkdrop
Inkdropは2年前に正式ローンチしました。初期ユーザはベータ時代に集めました。今のところ大きなメディアに紹介されたことは一度もありません。おそらく、当初からEvernoteをはじめ似ているアプリは沢山あったからでしょう。広告も一度も使ったことがありません。それらには頼らず、専ら既存ユーザをより喜ばせることに集中しました。並行して、自分のプロダクトやフリーランス生活での上手く行った戦略をブログに書き綴りました。これらの活動が功を奏して徐々に口コミを生みました。
月5ドルの自作サービスで最初の500人を集めるまでにやったこと
- ゆっくり成長させる。ブログで見せる。
- 口コミづくりとして、ユーザーを大事にする
上の記事では、初期ユーザーの話はあまりないのですが、ユーザーとどう向き合うか、どう成長させていくかのやり方が書いてあるので、大いに参考になりますね。
初期ユーザーとしては、ベータ版で集めたとあるので、それらの人が価値が伝わる人やコアなファンだと考えてそこから口コミで広がっていくという印象です。短期的な成長を一旦おいておいて、どう中長期で時間をとったら向き合うか。そこがこのInkdropから得られる最大の知見といえるでしょう。
なろう廃人のすすめ
ストック型のCGMサービスにするときは
初期コンテンツは自分で作るor外注しかないと思う。
自分は40ジャンル作り、300以上おすすめ小説投稿して 50レビューくらい書いた。「小説家になろうのまとめサイトを作る」
個人開発したWEBサービスをGoogle1位にするまでの戦略を語る
と決めてから、ブログに15記事、おすすめ小説記事を書いた。
- コンテンツは自分で作るという熱量が大事
- やる前に需要チェックとしての記事を書いてGoogle流入があるかどうかを確認
初期ユーザー数は確認できませんが、月間120kPV以上ということで一定の初期ユーザーがいると想定できます。
ブログマーケティングとして、記事を書いておいてどれくらい流入があるかチェックするのも、ブログを書くことに抵抗がないならすぐに試したい施策ですね。あとはやはり自分で作っていくということで、開発者は300程度はおすすめ投稿をしているし、というところが目安になりそうです。
個人開発なら個人の熱量が全てといっても過言ではないでしょう。その熱量サイズがそのままプロダクトに直結するし、ユーザ満足に直結するという感じですよね。
bosyu
リリース日初日は、多くのインフルエンサーに使っていただいたり、半日で1000ユーザーを超えてみんなで盛り上がりました。
bosyuというサービスを作って譲渡するまでの流れ
- PRTIMEのリリースで1300人ほどにリーチして、ユーザーを獲得
というのが初期のやり方だと思われます。もう少し最初にユーザーがいたかとかは上の記事から分からないので、半日で一期に集まったという理解です。
坪田さんの狙いとして「自分で使って数人採用できれば採算が合うような気がする」というところの肌感も適切な気がします。これは開発してどこを目指すか着地するかというところで、MVP事例を作るというメタ感もありますので特殊かもしれませんが、サービス開発においては別に特殊でもないのかなと。
こういうのってお金を多数掛けるところでもなく、MVP事例としてというところで秀逸になるので、うまくいったことはすごいですが、それ以上に撤退やリソース管理も適切だったとこれも結果論になりがちですが想定しているのでやはり素晴らしいと言えそうです。
スナックミー
スナックミーをスタートして、最初のお客様は広告経由で集客しました。100人ぐらいです。その後、本当にスナックミーがサービスとしてニーズがあるのかを探りたくて、一気に広告を止めてみたんです。
すると、予想以上にお客様が増えていきました。TwitterやInstagramに投稿してくださる方がとにかく多くて、投稿を見た方が新規で購入してくださるという流れができていました。
UGCを起点に開発し、流通させていく。スナックミーが切り開いた新たな販売の在り方 #ザ・プロフェッショナル
- 100人は広告経由で集客した
- その後は広告停止してオーガニックで増えた
- とくにTwitterやInsragramに投稿する人が多かった
本記事はUGCつまりユーザーが投稿する行為、コンテンツに関する記事です。そういう文脈ではあれ、上の発言は代表の服部さんのコメントとなるので、その通りなのでしょう。
最初に広告を出してLPなりティザーでどう判断されるかを見るのはありですね。それもグロースという意味でなく、ニーズ検証という意味合いで意図的なら良いのかなという印象です。
PAPAMO
PAPAMOという子ども預かりサービスのプロトタイピング時の事例です。こちらの本のLesson14(Kindleでは位置713)が参考になります。
- 小規模な体験会を16回、3店舗でプロトタイピング
- 価値検証は子どもが長時間集中して楽しめること、多様なスタッフが子どもと接することで子どもの個性が引き出せること
- 創業者は会社員で仕事をしながら母親に100人以上インタビューしている
本書のこのあたりは「リモデル」というピボットなり、価値検証で修正していくところが解説されていてとても参考になります。
さて、上の本では直接ユーザー数は言及はないはずですが、
実は「PAPAMOスクール」は正式オープン前にプレオープンを3教室で実施しています。その結果、2教室でキャンセル待ちが出るほど盛況だったようで、参加者アンケートでは、100%の保護者の方に満足の回答をもらえたとのことです。
少子化時代に「習い事教室」を成功させた企業の徹底的な仮説検証
という記述を確認しました。プレオープン=プロトタイピングですね、正式オープン前のアイデア検証時で手応えを得ているのがポイントというわけですね。現在はPAPAMOはオンライン運動教室としてピボットしていると考えられます。
インタビュー数がどうというよりも、ユーザー視点やユーザーが感じる価値、PSFを丁寧にできるか、そこが思い込みだけではないか。当然妄想でも最初はいいのですが、形にするには妄想のみでは厳しいですよね。
uniiリサーチ
unii(ユニー)リサーチは、定性調査をパネル募集からヒアリングまで手軽に出来るサービスです。2020年9月リリースです。このサービスはLIFULLの新規事業コンテストから出てきた事業となります。
代表の浜岡さんが語っている点が参考になります。
構想だけは固めた上で、様々な会社に10枚程度の拙い営業資料を添付してメールを送りまくりました。新規事業に取り組む大手企業やコンサルティング会社などのリストを作り、約100社に対して、3名のチームメンバー総動員でメールを送っていきましたね。すると、そのうちで返信率は10%、受注は5社と、想定以上に良い実績が出ました。この時にニーズが確信に変わりました。
【LIFULL_uniiリサーチ】「事業開発の不」を解決する新規事業への挑戦
つまり、
- 見込み客(ここではtoB)に対して100社送る
- 返信率は10%で10社程度
- 受注出来たのは5社なので、全体で5%。見込み客のうちなら50%
- これを持ってニーズの確信とした
ニーズとして仮説は大事ですが、それを試してみて実際に手が動く客がいるかどうかは大事だと思います。ここでのリスト対象は大手企業で新規事業をやっているところやコンサル会社などというところでターゲットを絞って出してみると。返信率10%は結構高いのではないかなと肌感で思いますが、それ以上に発注した企業が取れたのが大きいですよね。
こういう泥臭いことが大事だなと痛感させられるところですね。
オイシックス
オイシックスは宅配で有機野菜などを届けるサービスです。設立はネットバブル頃で2000年とされますが、この時はまだまだブロードバンドもADSLが出てくるかどうかくらいでなかなかインターネットで買い物自体が定着してなかった頃です。そこでも踏ん張っていく姿勢が非常に参考になると思います。
設立当初は1日2件程度の注文しかなく、カスタマー担当は3人で仕事を奪い合うというところで、仕掛けたのは2つの取組みです。また当時は多くの注文も、社員の友人や家族や親戚ということだったので、初期ユーザー獲得といっていいでしょう。
以下、「ライフ・イズ・ベジタブル」を参考にしています。
- 雑誌まだまだ紙ベースで、ネットコンテンツ作成など充実していないので、コンテンツが欲しいはずと想定。そこでレシピを無料提供してコンテンツとしてもらい、その代わりリンクをオイシックスに貼ってもらう。レシピ自体はシダックスが出資関係にあり、シダックスに対してはレシピをデータベース化する(紙管理だった)代わりに、無料でレシピを使わせてもらった。それにより注文増につながった(P.140のわらしべ長者プロモーションの項参照)
- 「相互リンクデイ」と名付けて、朝10時から午後2時までを、ウェブ日記や日記サイトなど個人ページ運営者にメールを送り相互リンクをお願いした。1日数百リンクをはってもらうことに成功した(P.144地道にがんばる競争)
僕はこの2つが象徴的なアイデアであり、地味ですが楽しくやるということでこのビジネス、いや著者の考えが反映されていると感じました。
他にも、P.185のおいしい廃棄物は「形が悪いなす」を売る話で、訳あり商品といって今は定着しているものですね。P.214のきゅうりのフィードバックは、当初農家さんに大量発注出来るわけでなく小ロットだったため、それならばということでお客さまが「美味しかった」という声を届けるという取り組み。P.215の農家オブ・ザ・イヤーは新年会の余興から始まった、「美味しい」という声を年内で最もお客さんからもらった農家さんを表彰するもの。
どれもアイデアに溢れていて、当然辛いこともあれど、楽しくやっているのだなというところが伝わってきます。
ヴェルク
boardというサービスの話です。
受託の会社が資金調達せずに自社サービスを立ち上げて、有料導入1000社に行くまでの経営・受託とのバランス(BPStudy発表時の補足)
こちらの記事は資金調達せずというところがメインで、そこにあるスライドも主旨は同様です。もちろんこれも参考になるのですが、1枚だけ初期ユーザー獲得の話があったのでそこを注視してみます。
[slideshare id=79318627&doc=bpstudy120-170831110712]
スライドP.59にあるところでは、
- 製品開発中からTwitterでつぶやいて「何か作っている」認知を身の回りの人に認知してもらう
- β版リリースで、それらの人がFacebook/Twitterでシェア。Facebookとの相性が良く、アーリーなユーザーが期待感から広めてくれた
というわけで、地味につぶやきつつ認知を作り、本サービスは請求書等のバックオフィス業務の効率化システムなので、起業家、スモールスタートや零細規模の会社などに相性が良かったということでしょう。
記事も驚きますが、2014年8月に始まって受託業務をしながら、100社は2015年3月に達成。ペース感は認知と共に増えていく形ですが、3年ちょっとかけて1000社まで持っていくスタイルは、まさに1000者のファンがということを地で証明するストーリーだと感じました。素晴らしいですね!
家いちば
家いちばは空き家などなかなか買い手がつかない物件などを直接売買できるマッチングサービスです。この手の走りと言っても良いのと、今でも動いているので老舗感すらあります。
「家いちば」は空き家問題の救世主となるか?事故物件から廃墟まで、何でも売れるその仕組みに迫ってみた!によれば、
起業後の1年間は問い合わせはあったものの、契約とならなかったようです。どうすればいいかの試行錯誤があって、やっと1年経ってから1件目が決まりそこから加速していったという話です。
1年間をどう捉えるかですが、自分が思い描くところでのユーザーとのギャップ、環境とのズレを修正して「試行錯誤」していくことで、つなげていく。
売っても買っても幸せに 藤木哲也著『空き家幸福論』でも書かれていますが、やはり合理的経済的なロジック、いわゆる今までの資本主義とは違う世界線という感じを受けます。ここを丁寧に掘り起こしていけるか、感じられるかというところがポイントですよね。
当然従来資本主義に乗せてしまうと、いわゆる成り立たない、それでは商売にならないとなるのでそこをどう解決していくか、折り合いをつけるかかなとも感じられます。
会計クイズ
会計クイズを解くだけで財務3表がわかる 世界一楽しい決算書の読み方がベストセラーになっていますが、この会計クイズの成り立ちです。なお、WebサービスはFundaというものがあり、こちらはブラウザ上でスライド形式で学べるのでより双方向性がありますね。
SNSで月1,000万回みられる「会計クイズ」たった一人ではじめたコンテンツが人気に。成長の理由は「0次市場」での検証プロセスでの最初の取り組みが興味深いです。
会計クイズってどういうものかというと、著者である大手町のランダムウォーカーさんがTwitterに挙げているので見てみて下さい。
その上で、この会計クイズをどう作ったかを一部まとめると、以下のようになります。
- 著者は仕事上で会計に慣れ親しんでおり、会計クイズで遊んでいた
- シェアハウス(で著者は住んでいた)内のメンバーにそういう楽しみとしているクイズを見せたら「全然分からない」という反応あり(笑)
- どうすれば決算書に馴染みがない人にもクイズを楽しめるかを改良し始める
- 再度シェアハウス内の勉強会では、180人中100人が参加
- その会計クイズをTwitterで投稿すると、3ヶ月で1万フォロワーへ(2022年7月8日時点では10万フォロワーとなっています)
ということで、ここでいう0次市場とは、サービスのコンセプトやアイデアレベルのものを検証していくところといえます。
そもそも著者がクイズを楽しめたのは専門知識があり、実践でやっているからだったんですよね。会計を知らない人には「?」でしかなかったことを何気ないやり取りで知ると。ここで明らめるとか、ターゲットではないと思えば終わりです。
しかし、著者は明らめず、そもそも「会計」の面白さを知ってほしいという熱があった、それは会計への愛だと思うのですが、それでクイズを改良して楽しめるようにしていったということですね。例えば、PLやBSの言葉が難しくても、簡易化した図に落とし込んだり、クイズとして比較すると分かりやすい企業、トピックや切り口がおそらく「面白さ」「新しさ」だったのかなと思います。
ベストセラーとなったのも、僕も買ったのですが、会計に馴染みがない人がまさに僕ですし、そういう見方や視点があるのかという人が多かったのだと思います。
コンテンツはクイズということでそれ自体は特殊ではないしありふれたものですよね。でも、会計という仕事や知見を入れること、かつターゲットが会計専門家ではない、会計に馴染みがないとしたことで面白いアウトプットになったといえそうです。当然この著者の粘りややってみてどうか、会計愛というのも無視出来るものではないでしょう。
それ以降店頭で分かりやすい会計本みたいなものも類似のものが見られたりしますが、クイズ→分かりやすい→学びになるというところは本書が一線を画しているのかなと感じています。
自分が面白いものを近くの人、近しい人に聴いてみて反応を探る。これ意外に見過ごしているかもしれませんね。またそこで駄目なら明らめずに改良してみる。そこで非会計の人の視点を得ていくのもユーザーの解像度を上げることになりますよね。
エアークローゼット
エアークローゼットは服のサブスクサービスです。
詳細はこちらの9割に否定された「ファッションレンタル」のサービスが7年で黒字化、売上28億円に。会員70万人「エアークローゼット」の裏側と「新しい習慣」を生むサブスクのつくり方をどうぞ。
最初の顧客アタック部分を取り出すと、
- ファッション業界関係者など200人にヒアリング
- レンタルで服を借りるのは9割方ありえないという手応え
- プレスリリースでコンセプトを出したら口コミで話題に
- 初期段階の3ヶ月で2.5万人の事前登録者を獲得
これだけみると出来過ぎとは感じつつも、当初業界関係者に聴いたヒアリングですよね、それで否定されつつも、本当にそうなのかな?と疑って試したのがグッドですよね。
いきなりサービス当初で事前登録がこれほど集まるのは成功といってもいいわけですが、そこでしっかりと形にしていったのは流石ですよね。2022年7月29日では上場予定となり素晴らしいですね。
この事例ではやはり、合理的な事由というか、とくに関係者の視点はヒアリングしてファクトは取る。その通りだとは思うけど、合理で事業は出来るわけでなく、情緒や感覚とずれていたり、生活者の視点では全然違うこともありますから、そこを見ていく(捨てないこと)が大事だと感じられました。
つくりおき.jp
- 簡易LPを作りFacebook広告でテストマーケ。事前登録のCACが約1,500円だった
- 登録者は子育て中主婦の方が多かった
- 簡易LPは1時間ほどでペライチで。事前登録者50名にヒアリングして検証
事前登録から検証期間は約9ケ月あり、正式リリースでプロモーションし有料登録が30名という流れ。事前登録をしっかりテストマーケティングして子育て中主婦を把握し、その中でも体験価値としてもっとも刺さるものを考えたのが素晴らしいと言えそう。検証に9ヶ月かけたサービスが約2年半で450万食を突破。「つくりおき.jp」が語る、公開の翌月に「継続率100%」に至ったサービスづくりの事前検証のポイント。
最初のユーザーとしてはやはり9ヶ月間のテストマーケティングが肝で、そこを磨き込んだので正式リリースでも有料登録がありと理解。
テストマーケティングをすれば絶対成功するということでなく、何をテストするか、どういう仮説を立てていて検証したいのか。そうであれば9ヶ月間はそこまで長くはないとも言えそう。
あの日のはこだえ(きくらげ栽培)
日栄交通というタクシー会社の新規事業の取り組みです。全く違う分野でチャレンジして、より利益率が高いビジネスにしていくところが非常に面白く感じました。
「きくらげ栽培」で空き家問題を解決へ 南浦和のタクシー会社の挑戦からすると、最初の顧客獲得は、
- 自社栽培出来たきくらげをメルカリに出品したら、翌日購入された
- 友人や近所の人に配ると美味しい!という声を得た
- メルカリで購入した人からリピートの問い合わせが来た
というわけで、メルカリで売ってみてそこで手応えを得たんですね。これが今っぽいといえば今っぽいですが、昔なら違うものを使ったかもしれませんし、ITを敢えて使わなくてもいいかもしれませんよね。
こういった小さな「確信に至る小さな出来事」を積み重ねたからこそこのビジネスは始まったと言えそうです。ちなみにエアークローゼットと同様で、きくらげ栽培は夏が旬であり、ハウスなどで冬場でやらうと光熱費がかかりすぎて通年栽培はできないから辞めたほうが良いと言われたようです。このあたりは通説=業界の常識があって、それを違う方法で出来ないかを考えたから出来たかもしれないですよね。
休日ハック
あらゆる人生を「痛快」でおもしろくする。営業職7年で得た気付きをサービスに展開した休日おまかせサービス「休日ハック!」の誕生秘話に迫る。
創業者は同じようなダラダラした休日を過ごすのが良くないと思って、友達に1万円を出して休日のプランニングを依頼したというのが面白いですね。
とくに最初の顧客獲得数などは書かれていませんが、
- まずは友人に何人か声をかけて予定を立ててもらう。それを自分で体験する
- 次に友人の友人で立ててもらうという実験をする
- 予想以上の好感触があったので友人を巻き込みながらサービス化
やはり、身近な人で話せる人、ここでは友人ですが、そういう友人に声をかけたのが大きいですね。
細かいところでは友人がこの場合実験であれ、ターゲットに近いかはおいておいて、実験してもサービスの世界観とそこまで違っていなかったのもポイントかもしれません。例えば友人がいてもその人が明らかにターゲットと異なる場合はマイナスにもなるからですね。
実験をまずはしてみる。それで手応えを確認する。言い尽くされているかもしれませんが、それが大事だなと痛感しますね。逆にいえばここで実験しない、友人に話してみない、というところで止まる人も多いのかもしれないですね。
MENTA
プログラミングなどに関して教える人(メンター)が探せるサービスです。2018年6月頃にリリース。そのリリース前に、
- MENTAオープン前にユーザーをTwitterで集める(以下のTweetが該当)
- 50名想定が、200名近くの事前参加者あり
- 初日から流通額で9万円発生し手応えを掴む(「自分のサービスで生きていく<個人開発の教科書>位置443より)
詳細は、自分のサービスで生きていく<個人開発の教科書> Kindle版でどうぞ。入江さんは数十個サービスを作っていって、個人開発として自分が欲しかったものを作りそのMENTAがヒットしたんですね。その後はLancersに売却して自身も代表としてサービスを運営しつつ、現時点では別の方に代表を譲っているかなと思います。
僕自身はMENTAが始まる頃を見ていて、このサービスがいけるかというと厳しいのではないかという見立てでしたので、僕の見立ても大したことないなという感じですね(笑)
リリース半年後はPMFとして当初は何でもというか色々なメンタリングができたんですね。音楽とか、英語とか、それこそなんでも。でも、それがエンジニアによっていることから、プログラミングに絞っていって成長していったと。
ここで学べるのは、やはり最初にユーザーを集めること、リリース前からですね。事前に集められないならやらないのも賢明な判断かなと思います。
どうサービスデザインするかは世界観次第
色々な事例を見てきました。
泥臭いというか、まあ最初はそんな感じでしょうし、楽して成長ってないのが伝われば何よりです。そんなことを微塵も思ってない人ならそのまま知見になるはずです(笑)
やはり見てきて言えることは、自分なりの法則や勝ちパターンや検証スタイルがあればそれは武器になるので強いということですよね。僕も自分で投稿というのはやれるスタイルでかつ結果が出たのでそれはオススメしたいし、自分の熱量チェックにもいいですよね。ないならそのアイデアというか熱量で勝負したのが敗因となりますから。
あとはちゃんと考える、つまり手抜かずにプロダクトがない時点でしっかりと詰められるか。詰めていければ何かふわっとしたものでも、何かが見えてくると。あとはその価値の再現、検証、自分が使うだけでなくユーザが使うのでそのターゲットが価値を再現したり、何か独自の価値を見出してくれるかですよね。
世界観と書いたのは、Aというサービスではセオリーや正しい具体的なやり方も、Bというサービスでは違うということですよね。セオリーみたいなのってあってもいいし、押さえておくのもいいのでしょうが(例えば問い合わせがあれば対応して改善するとかですよね。でも、それも個人なら限界があるので適度でしょうし、伝えた意見が全て反映されるわけではないですから、見極めが必要ですよね)、それはそれとして世界観と合致するほうが大事な気がします。もちろん、世界観があれば何をやってもいいなんて極端ではないですけど、そこらへんの感覚が難しいというよりも、正解がないので、自由度が高いからやりがいがあるし、面白いのだと感じました。
そこに面白みを見いだせないとなかなかこういうふわっとした中でサービスを作りきる、検証しきる、やりきるのは大変だろうと思いつつ、何かヒントになれば幸いです。他に面白そうなものがあればまた追加していきたいと思います。
筆者プロフィール

- 「シゴクリ」運営者。アイデアの力でお客様に貢献するゼロイチ大好きアイデアマン。ビジネスアイデア相談実績等は200超を超える。好きな言葉は三方良し。詳しい自己紹介、仕事実績も合わせてご覧ください。お仕事メニューやお問い合わせはお気軽にどうぞ。
最新の投稿
 アイデアネタ2024年7月26日思い出はデジタル化はできないが、思い出のきっかけは常に残せるのかも。
アイデアネタ2024年7月26日思い出はデジタル化はできないが、思い出のきっかけは常に残せるのかも。 アイデアネタ2024年7月25日るるぶの豆本化に学ぶ。小さくしてみたら面白いかも。
アイデアネタ2024年7月25日るるぶの豆本化に学ぶ。小さくしてみたら面白いかも。 思考・考え方・メモ2024年7月25日キャリアモデル開発士認定証頂きました。
思考・考え方・メモ2024年7月25日キャリアモデル開発士認定証頂きました。 思考・考え方・メモ2024年7月25日シゴクリラジオゲスト回。キャリアモデル開発の長沼さんから刺激をもらいました!
思考・考え方・メモ2024年7月25日シゴクリラジオゲスト回。キャリアモデル開発の長沼さんから刺激をもらいました!