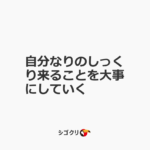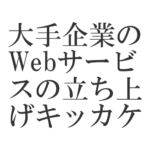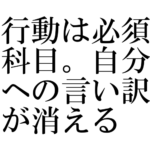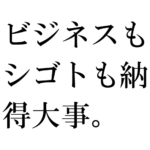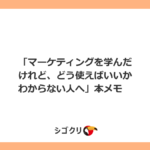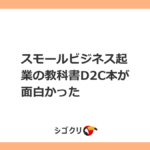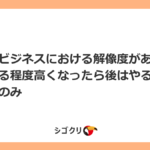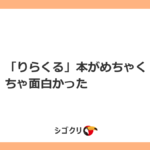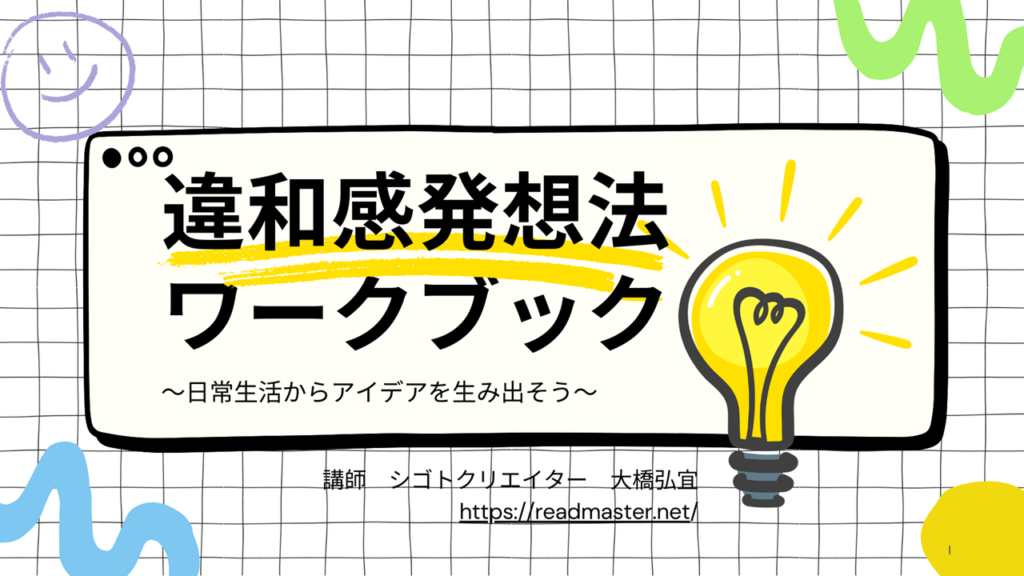社会を面白くするというコンセプトを再認識した
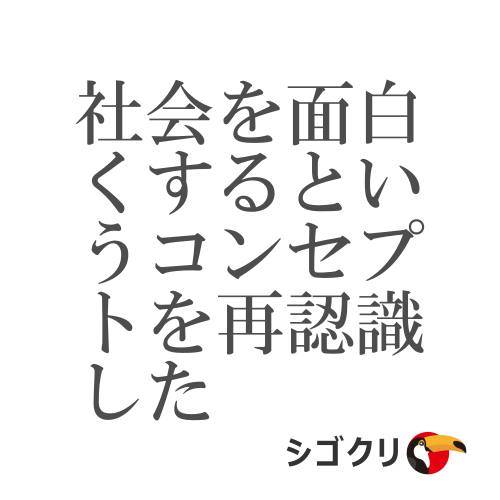
ちょっと前に良かったネタから起こしてみます。
ネタ元は、ankeiyさんが書かれた
です。
また、発見したのはthe bridgeの記事である、
世の中は事業のタネで溢れているーーライザップ、ユニクロ、ZOZOSUITが変えた世界とは【前編/ゲスト寄稿】
世の中は事業のタネで溢れているーー事業づくりで大切にしたい「3つのこと」【後編/ゲスト寄稿】
でした。the bridgeのほうが読みやすいですが、原文と強調表現が違っていたりするので、お好みでどうぞ。
以下、引用箇所はすべて元ネタの記事からです。
目次
本質的な価値の捉え方
非常に面白い記事で、タイトルどおり世の中は事業の種で溢れているということを「証明」というか、示す内容です。
いちいちしびれていたのですが、ドリルの穴の例では、そもそもなぜ穴を開けたいのかまで抽象度を上げることで、より本質に迫っています。記事では、ドリルの穴のために、ドリルメーカーでなく、ドリルレンタル事業→ドリルシェアリング→家具メーカーというように、どんどん上に上がっていってます。面白いですね。
著者はそれらを
たった一つのドリルの穴からこんなにも様々な事業やサービスが生まれる可能性があるのです。
という形で指摘しています。実際にドリルの穴という話も深掘りまたは抽象度を高めていけば色々なレベル感での気づき、種、事業となるわけですね。
これだけで既に学びが一杯ですね。
例えば、本を読み放題というものが流行っているとすると、「実は読み放題されている本は大分偏っているのではないか」といえるなら、「特定のベストセラーだけ読み放題」とかでもいいといえるし、「読むのすら面倒だから、要約があればいい」ならば、フライヤーみたいな要約サービスになりますし、音読がいいならaudiobookとかですよね。
別視点でいえば「本屋不況みたいに言われるけど、本を売りたい人が一定数いるから、それらの人向けの販売支援ツールが売れそうだ」と思えたり、「いやいや電子書籍で漫画とかだけでしょ」と思うなら、埋もれている漫画家を発掘するようなサービスとしたり・・・たくさんの小さな気づきから広げられるわけですね。
これらは日々アイデアを考えたり企画するということから賛同というか、まさにまさに!という膝をたたきまくってしまう感じです。
価値の再発見、新しい価値観との出会い
ぼーっとしていて勝手に面白い価値に出会えることはまずないでしょう。とはいえ、日々忙しい!といって追われていて見つかるかというと分からないですが。
上の記事で、価値観の再発見というところで言われているのは、
- 天体望遠鏡メーカーが突破口としたのは「星を見せる会社」というコンセプトアイデア。優先順位が「望遠鏡をつくる」から変わっていく。
- ライザップはダイエットプログラムを「自分で目標にたどり着けることで自信を得る」と再定義した。これは痩せるという以上の価値がありそう。
- ユニクロはファッションを「上から目線でなく、消費者目線で特別なものでなくていい」という価値を見せた。コモディティというのを楽しむまたはその上で楽しむ感じですかね。
- ZOZOTOWNは「サイズをメーカーでなく、ゾゾスーツによって自分で決める」という価値観の転換をした
細かいニュアンスは元記事を読んでみてください。どれも価値観とかコンセプトとか、そのアイデア自体が面白いのもありますが「何が本質か」を見極めてそれを「こうなったらいいんじゃないか?」を提案していると言えます。
その提案に「乗った!」人が多ければ売れるし、時代をつくる商品やサービスになるわけですね。
著者はそれを、
「従来の価値観をひっくり返すような(あるいは否定するような)新しい価値観の発見がある」
と書いています。
実際は価値観を変換させるものは、批判されたり否定される圧も大きいと。実際に駄目なものもあるのでしょうが、その「圧」があればあるほど変わると「新しい」わけですね。大富豪のカードゲームを思い出しますね。桃鉄のキングボンビーとか(笑)
こういう価値観にどう遭遇するか、遭遇というか見つけていくかは、上で書いたように「本質」を見抜いていくこと。今体験している「これ」ってなんだろうか。何なのだろうか。そこを「まあいいか」でなく「なんだこれは」と立ち止まっていくことなんじゃないかと僕は思いました。
その面倒くさい作業というか、違和感にきちっと向き合っていくことで、本質というコアであり濃いものが必ず見えると。その発見はものすごいアイデアだし、価値なはずですから。
新しい価値観の発見じゃないパターン
著者は逆のパターンとして、そうじゃないパターンを挙げています。上では、本質であり、新しい価値の発見の例を挙げたわけですが、その逆です。
- 美容室予約サイト事業を立ち上げたい。理由既存サービスが広告単価が高いし利用者は不安がある。だからそれより価格を押さえればいける。けど、既存の価値観を揺さぶってないし、新しい価値となってない。
- インバウンド向けの事業をやりたい。情報サイトとしてもっと面白いものを作れる。けど、これも既存の延長だし、既存の価値観でしかない。
上の2パターンが必ず失敗するとかではないんでしょうが、わくわくするような面白さを感じるかというと微妙でしょう。起業家自身は口ではいけるというけど全くワクワクしてないなら、その伝える熱量や人を巻き込める力も相当少ないというか、ないに等しいわけです。
美容室業界における本質の価値はなんだろうか。例えば美容師の労働環境が問題ではないか。でもそれらを通してやりたい、なりたい憧れる仕事であり手に職をもつということもである。一方で不安もある。そういう中で、美容などは人の生活にとって欠かせないみだしなみの行為。であるならば、なぜ人は美容院にいくのか、美容師に頼むのか、そこで何を求めているのか。癒やしという言葉が流行ったように人は会話を求めているかもしれない。癒やされるお客は癒やす美容師からパワーを奪っているともいえるかもしれないならば、美容師自体がめちゃくちゃ疲れているのでないか。例えば美容師を癒やすというメタ癒やしサービスができないか。
美容師になるのが目的でなく美容師として仕事を続けるのが一定の目標ならば、そういうキャリアの育て方、成長の仕方はどこまで整備されているだろうか。他の業界の人材教育モデルを使えないだろうか。それが疲れている美容師のためになるのではないか。またはキャリアプランの新しい提示、エコシステムの構築になるのではないか。
みたいな、これが本質かはおいておいて、僕としても市場があるからやるとか、儲かるからやるとか、だけでない視点としての価値観の発見、新しい価値の提示こそがやはり面白いなと感じたわけです。
日常に事業のネタは溢れてる
僕も同感です。
著者のまとめは記事を読んでもらうとして、上で書かれたようなことを再度まとめています。
ここから本記事で言いたいことでもあるのですが(笑)
なんかこう書いてくると、事業を考えるということは、すごく難しいことをやらなきゃいけないような印象を持たれる方もいるかもしれませんが、逆に事業のタネは、私たちの周りに溢れていると思うんですよ。なぜなら、私たちはいつも「その時代の当たり前」に取り囲まれて生きているからです。
実際その通りで、僕が生きている今の社会は今の習慣や感覚で成り立っています。もちろん少し変わったことをやれば違和感とか、色々発生します。
逆に何も感じない、そのままを生きているなら「自然」ですが、引っ掛かりがなければ、発見はできない気がします。つまり、「差」です。
今の社会では当たり前になっているが、少し先、少し前では当たり前ではないことがたくさんある。今この瞬間でも少し違うことや違和感や差を感じることがあればそれこそがまさにビジネスのヒントになると言えそうです。
例えばブログ記事を書くときに「タイピング」が当たり前だと思っているわけですが、これを「音声入力」が当たり前になると、ブログの書き方が「カタカタカタカタ」と音をたてる+黙っていることでなくなり、「ぶつぶつ」いいながらうるさい感じになりますよね(笑)こういう価値の変化や変わり目でどう感じるかです。音声入力をやればいいというよりも、「カタカタ叩くのと同様のアウトプットが出来る」とか「口で言うことで思った以上に整理できる」とか、違う切り口でいかようにも見せられるわけですね。
立ち止まるというのは物理的に人々の進行方向に乗らないということでもあり、精神的には「何が起きているか」を観察することだとも言えます。
著者は最後にこう締めています。
若いとか高齢とか、経験があるとかないとか、金持ちだとか貧乏だとか、偉いとか偉くないとか、まったく関係ない社会で評価されるわけです。それも事業を起こす素晴らしさですね。そして、なんと事業を考えることは無料w誰でもできる最高に楽しいゲームなんですよ。
ゲーム感覚とかでのビジネスや起業は語弊というか誤解を受けそうなんですが、実際にはどうすると良くなるかの改善運動をやり続けるという感じに近いと思っています。ゲームという言葉がかなりイメージが分かれるのが難点なだけでしょう。
年齢や資産の有無とか社会的地位に関係なく、これから事業を起こす、それは別に小さい事業であっても規模関係なく、それによって評価される。それは多分ですが、「事業を起こすことで、新しい価値を提示し、それで社会が変わっていくというのが醍醐味」というのが著者の言い分ですが、全くなるほどなあと感じました。
Whyから入る方が楽しい
形としてのWhatからでなく、なんでやるのかこれをしたいからというWhyから入るほうが楽しいという話でもあるなあと。
つまり、何かしら「既存の延長」に過ぎない、つまり既存と同じであるような「見えるモノ」は想像ではないんですよね。Whatとしては見えるわけで、ものとしてはありもの。かき氷屋さんがあるのに、かき氷アイスを作って売るみたいな延長感ですね。しかもその理由は売れそうだからだと寂しいなあと。それをやれる人もいるかもですが、僕はそういう感覚ではやれないし続かない感じがします。
もちろん、厳密には「やったからあとで理由付け」できるのもありますが、好きだからとか楽しいからやってお金になるのと、お金になるから好きというのは似ているようで、異なっていて、最初に感情として好きとか面白いが来ないと一生「お金があるから、儲かるからやる」しかないようなとも思ったわけです。
なんで生きるのかとかと僕は強烈に紐づけたほうがいいとか思ってるくらいなので、これは僕の勝手な話ですが、それによってモチベーションとなり、ぐるぐる動けるならそっちでやったほうがいいというライフハック的な感覚ですね。
そのWhyについての理解は自分が100%分かっていればあとは他人や社会との調整という感じですかね。当然ぶれていけるとおもった自分のジャスティス(笑)が全く勘違いだったということも視野に入れつつですね。つまり、Whyに対する理解が100%自分でOKなら、あとはどう形にしていくか調整していく作業でありゲームという感じになります。
Whatから入ると、結局Whyの先延ばしとなります。うまくいけばそれでいいだと、それの繰り返しですがそれが疲れないならいけるかと。ただそのWhat→うまくいった→Whyが来る前に→次のWhat→・・・は相当人を選ぶ気がしますし、僕は無理だなと。
それなら自分なりの直観をまず設置する。Whyを攻める。そして形にして検証してそれでどうか。のほうがうまくいきそうな想像やイメージ、先の絵が見える感じがしました。
絶対にWhatありきだと駄目とは言いませんし、絶対にWhyありきだといけるとかもいえません。自分に合うかどうかって感じですね。
僕がやりたいのは・・・
実際に僕がやりたかったことは、お金儲けを否定すると稼ぎたくないのかというカウンターが飛んでくる(飛んでこなくても言いやすいベクトルがある)、社会のためや人のためというとこれもカウンターを飛ばしやすい(笑)なあと思うわけです。
自分が何をやりたいのか、これこれをやりたいというのはなんとも重い感じがしますよね。
そういう意味で、同記事は「自分が見つけた、こんなのどうかなというまさにアイデア=新しい価値を社会に投げてみる」ことが評価される。
その試みが広がること=ビジネスをどんな人も、日常に落ちているであろう「種」からできるんじゃないか、という提案なわけです。
つまり、僕がやりたいのは、シンプルに「社会を面白くすること」なんだと、まさに10年くらい前に思ったコンセプトに戻りました(笑)戻ったというか、またそこに来たなあという感じです。
当時そういうコンセプトを提示しつつ、色々な人と話したと思うのですが「それはどういう状態になることなのか」とか「それは自分が面白ければいいのか」みたいな話もわりともらいました。今で言えばそれは大分ずれているというか、上で考えてきたことからいえば「自分もだけど、社会もそれいいかもねということを一緒にやる」わけで、それが良い感じで広がるならいいじゃないかという話ですね。
一方「社会のためにといって社会を乱す」(笑)ということもあるわけですが、乱すというのは何かをよく考える必要があります。単なる変化についていけない保守的な感覚なのか、それとも変化はしてもいいけど自分に不都合は嫌な不快回避行動なのか。正解はないですが、じっとしていることが筋がいいということってあまりないなあという感じですね。
そういう社会、今も未来もですけど、当然面白いという感覚がなければ生きている意味はかなり薄いです。面白くないなら、それで?となるわけです。もちろんそれで他人を批判することは微妙なんですが、少なくとも自分は自分を面白がっているかは使える自分指標だし、機能してきたなあとしみじみ思います。面白ければ何やってもいいとかは言い過ぎですが、まあ仕事として成立すればよりハッピーになりやすく、事業で大きくすればさらに面白いわけですよね。
このあたり、今回のネタ元である「新しい価値を提示し、広げていく作業」がビジネスであるならば、やっぱり関わってよかったし、楽しいなあと思えました。
というわけで、ぜひ上の記事読んでみてくださいね。
おわりに
シゴトづくりをしようとか、起業・副業しようとか、色々なレベル感や思いがある人がいると思います。その時、多分ですが自分の直観を信じてください。ここでの直観とは、「本質的な価値」というものに近いです。
それは言語化されてない「なんかこういうのではない」から始まり「これも違う」「似てるけどなあ」とか、微妙な否定から小さな肯定、様々な段階があるんじゃないかと思います。だからこそ、一発でこれだとはならないわけですが、そこを粘って粘っていくと。
粘れるのは当然自分が面白いとか、なんかこの考えやアイデア提示したら社会が豊かになるし、というワクワク感であり、楽しい未来が見えるからですね。
そういうのがあるから僕はシゴトクリエイターとか、なんか自分でシゴトをつくるのが楽しいのだ、人のシゴトづくりを手伝うのが面白いのだ、といってきたかというとそうでもない気がします。またあえていうことでもないのかなと思ったりしてきました。
でも、諸々の行動や思考過程を考えると、多分根底というか潜在的なものとして、土台として「社会を面白くする」というコンセプトがあったからなんじゃないか。それがなければまったく違う人生だったかもしれないし、少なくとも今のような生き方や感覚や考え方ではなかったと激しく思いました。これはもちろん肯定であり、今がいいのであり、またさらに成長したいし、やっていこうという再認識にもなりました。
ぜひ、あなたも、何か違うなあとか、ビジネス的なことをやりたいとか、チャレンジしたい、してみたいけどうまくいかないとか、そういう時は今回の「新しい価値」を意識してみるといいでしょう。
多分その場合は「遠くを見すぎていて足元が見えてない」=「日常のネタや気づきを拾えてない」、まずは目の前を観察することからとなりそうです。もちろん観察したらすぐ何かが見つかるわけではないです。ただその蓄積が必ず大きな気付きや価値観になって、それを通して事業やビジネスや形になって、それこそ僕のように「社会を面白くする」という自分の中でも忘れていた(笑)コンセプトを再発見できるかもしれませんね。
というわけで、あーだこーだいってますが、「自分で考えてビジネスやろうぜ!」ってことだけですね(笑)
筆者プロフィール

- 「シゴクリ」運営者。アイデアの力でお客様に貢献するゼロイチ大好きアイデアマン。ビジネスアイデア相談実績等は200超を超える。好きな言葉は三方良し。詳しい自己紹介、仕事実績も合わせてご覧ください。お仕事メニューやお問い合わせはお気軽にどうぞ。
最新の投稿
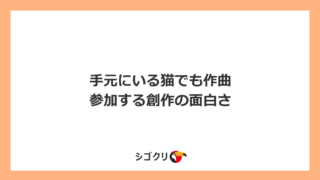 アイデアネタ2024年4月26日手元にいる猫でも作曲参加する創作の面白さ
アイデアネタ2024年4月26日手元にいる猫でも作曲参加する創作の面白さ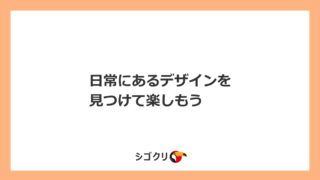 アイデアネタ2024年4月25日日常にあるデザインを見つけて楽しもう
アイデアネタ2024年4月25日日常にあるデザインを見つけて楽しもう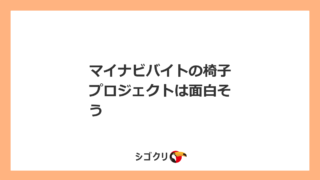 アイデアネタ2024年4月24日マイナビバイトの椅子プロジェクトは面白そう
アイデアネタ2024年4月24日マイナビバイトの椅子プロジェクトは面白そう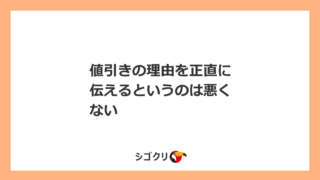 アイデアネタ2024年4月23日値引きの理由を正直に伝えるというのは悪くない
アイデアネタ2024年4月23日値引きの理由を正直に伝えるというのは悪くない
違和感で発想のやり方が学べます
LINE公式アカウント登録で無料で学べます。気になる方はチェックしてみて下さい。