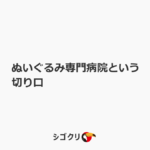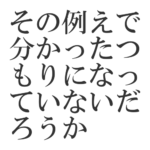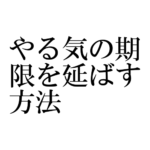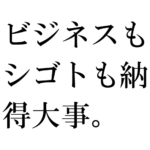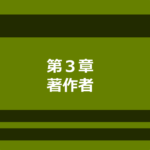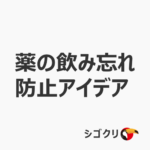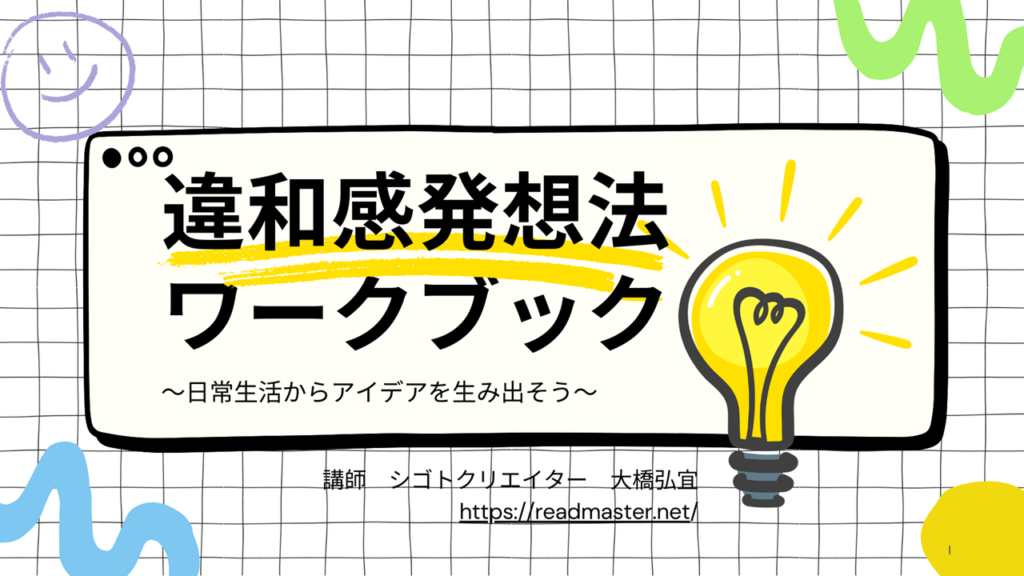最近読んだ3冊の本をアウトプット。集客、やる気、家族と超バラバラな感じでお届け。
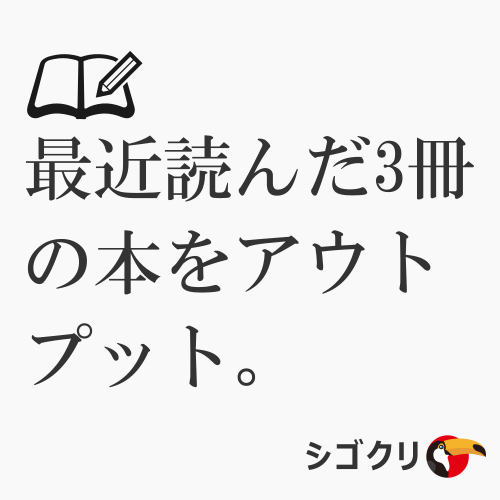
最近読んだ本のアウトプットです。
読書の秋というわけではないですが、Web本屋店長という切り口でおすすめしてみました。
目次
フロンターレの集客仕掛け人の考え方が凝縮された一冊
読んだきっかけ
川崎フロンターレというJリーグチームの集客アイデアが面白いという話を見て調べたところ、本書が出てきました。Webを漁るのもいいですが、面白そうだと思って買ってみました。
算数ドリルの事例が企画のエッセンス
天野さんというフロンターレのプロモーション部部長が書いた本で、単に集客の考え方でなく、スポーツビジネスなどの考え方も書かれています。
僕としては面白かったのはスポーツビジネスとかそういう専門的な視点でなく、どう特徴的な仕掛けをしているのか、アイデアの拾い方、考え方などが参考になりました。
最初の部分で出てくる「フロンターレの算数ドリル」といってもいいでしょうが、そのアイデアを形にした事例が出てきます。
簡単にいうと、海外のクラブチーム視察でアーセナルというチームで「教科書にサッカー選手が載っている」ということを知った著者が、早速日本でもできないか(地元川崎で)と動いた話です。
当然簡単にはいかないわけですが、つながった校長の心意気からテスト配布が実施され、最終的には川崎市内の小学校で配布することに成功します(確か)。
ここから学べることはシンプルですが深いなと。つまり、本書にも書かれていますが、同様にアーセナルを視察した人は多くいるけどその「教科書に選手が載ったこと」をどう受け止めるか。自分のチームや地元でやろうと思うか、そして当然ながら「教育委員会」や「営利企業の企画」が即教育で採用されるか、様々な課題が立ちはだかるわけです。
一発で解決する魔法はないので、一個ずつ形にしていくことで次のへの展開が見えてくる。まさに企画のお手本といっていいものだなと感じました。
読者対象はおそらく2つ
本書はそれだけでなく、様々な実例を紹介しています。一見すると「奇をてらった」と思われそうですが、そこは枝葉であり、一言でいえば市民が愛するクラブチームを川崎なりに実現するという軸があるから出来ることですね。
読者想定は、1つはサッカー・スポーツなどのビジネス的、マーケティング的視点で読むのもいいですし、もう1つは僕のように企画者が何を考えて仕掛けているかを学ぶために読んでも楽しめると思います。
算数ドリルの話はWebなどでももしかしたら読めるかもしれませんが、やはり著者の熱が感じられる本で読む、他の話も多数ありますのでそういうのがいいですね。
そして再度アイデアはどこにでも落ちているなあと再確認できる一冊でした。
実例が参考になるやる気を妨げるバグ探し
なんかやる気出ない人向け
心理学をベースにしたやる気がなぜか出ない人向けの本です。とくに無気力とか「やる気はあるのにできない」みたいな学習性無力感に陥ってる人にはおすすめです。
この何かやる気でないは、たまに起きる「面倒くさい」というレベルでなく、常に「やる気あるんだけどできない」みたいな話を指しています。それはある種の不具合で、バグ(プログラミング的に)と言えるわけです。
本書はそのバグについて理解をして、どうすれば対応できるかも解説されています。
万能感が原因となる視点が新鮮
本書では3つほど代表的なバグを挙げていますが、何とかしなければという万能感の事例が大きいと感じました。
ざっくりですが、なんとかしなければとか、神的視点、全ての事象は自分が回しているなどの「理想形があって動けなくなる」みたいな話です。面白いのは著者自身も同様にはまっていた時期がありそれを「何もできない不遇の天才」と書いています。
引っかかったのは「万能感」という言葉です。気にならない人ならいいのですが、僕はものすごく気になりました。
僕の解釈では「なんでも出来ることを経験しているし、実際に出来ることから作られた感情」と思ったのですが、本書では「なんでも出来ると思うことであり、実際にはむしろできてない状態だけど、出来ると思いこんでいる状態」が近いです。そうでないと文脈的におかしくなります。
本書でいう万能感の定義についてはおいておいて、ここでいう万能感はともかく「全て自分が回している」「神」的なものと考えてオッケーです。
これに対して、どう解決するか。これは対の概念として「快・不快などの本能のままで1日1回は行動すること」などと書かれています。
この快・不快という本能行動ができてないから、「自分ありの理想形判断」「運が良いというジャッジ」はどちらもバグとなります。
つまり、本能のまま何かやってみるという訓練をしてバグを解決していくことになります。こちらの世界は、エモい世界と思っていて、ただ感じる世界であり、考えない、無意識、事象が自分を回しているということになります。
無気力の原因として、自分がやる気がないだけであるとか考えがちですが、実は「やる気があれば出来るとか、そもそも自分が出来る理想形を作ってしまう、論理的な感覚」自体がバグであるということです。
もちろん理想を掲げて、なんでも出来るとか、論理的に考えて「行動」出来ていればなんら問題はないでしょう。ここでは空回りして動けない人に対する一つの話となります。
嫉妬による無気力
これはやや複雑ですが、嫉妬なども無気力になると書かれています。嫉妬をするのでなく、嫉妬をされるなど(それを表面的に言ってなくても)の行為が無気力になるという話です。
解釈がやや曖昧なので本書をぜひ気になる人は読んでもらえればいいのですが、嫉妬というのはどこでも起こりうることなので、嫉妬されている=優位?なはずなのに力がでないとは結構笑い話では済まないですよね。
そういう場合の回避行動や解決につなげる行動も紹介されています。
自分を攻めがちな人にはガチでおすすめ
本書を読んだのは僕自身が無気力を感じるのでなく、パートナーがおすすめされた本ということで読ませてもらいました。
実際に自分が肯定感が低いとか、成功経験が不足しているとか、自分に自信がない(私は出来る!)などの人には結構参考になる気がします。
自己肯定感が低くても行動したり、自分なりの動き方ができれば全く問題ないですが、「そういうできてない状況」に対して「全て自己責任」であるというか「自分が悪いのだ」という締め付けはかなり筋が悪いという話です。実際は「無気力を学習してしまった」が故であり、また「万能感」という出来る感であり、全て自分ありきというのが問題だということになります。
自立的(自律的)な考えと近いようですが、異なるでしょう。自立であれば全部やるというよりも、出来る部分もあるが、できない部分もあるということが分かっている。それらを受け入れているという状態でしょう。自分が全て出来るはずは、どちらにしてもやりきれないし、やろうとしても結局しびれて止まるということになるんですね。
文章自体は平易で読みやすく、心理学など専門的な知識がなくても読めます。
家族ってエモい。立体感のある主人公にリアル感を感じまくった
ナツイチでちょっと古いですが、集英社文庫の猫ストラップをもらうために買った一冊です。とはいえ、奥田英朗の本は前読んだことがあり面白かったので。
一番エモかったのはP.45
本書は6つの短編という形で家族というテーマで書かれた小説です。
最初の話は「虫歯とピアニスト」という話で、歯科医に務める事務員の小松崎さんとピアニストの大西さんがメインの話です。
P.45に書かれている大西さんの台詞がエモかったので引用してみます。
(前略)「プランAしかない人生は苦しいと思う。一流のスポーツ選手、演奏家、俳優たちは、常にプランB、プランCを容易し、不測の事態に備えている。つまり理想の展開なんてものを端(はな)から信じていない。理想を言い訳にして甘えてもいない。逆に言えばそれが一流の条件だ。だから人生にもそれを応用すればいい。(後略)」
(P.45 我が家のヒミツ (集英社文庫)、奥田英朗著)
この台詞にしびれました。思わず目に熱いものが(笑)
先程のやる気が出ない本ではないですが、全ての何かこの通りでうまくいくということはまずないでしょう。万能感というものがいかに無力かを感じます。むしろ、間違えるし、思い通りにならないからこそ、いくつものプランを持ち、用意周到に、または駄目だったら次をすぐ考える。それこそがクリエイターのシゴトだと。だからこそ人生もそのように考えればいいと。
勝手な想像ですが、著者の奥田さんはこの台詞から本ストーリーを組み立てたのではないかという感じを受けました。真相は分かりませんが、それくらいこの大西さんの台詞は心を動かしてくれました。少なくとも僕の。
他のストーリーもひたすらエモい
他にも、アンナの十二月、手紙に乗せてがエモくて思わず目に熱いものが。ほとんど僕は泣くことはないのですが、カフェとかで涙が止まらないのはまずかったです。
解説で大矢さんが説明してくれているのですが、なんで全く違う家族や性別も年齢も違う人達をこれほど丁寧に書けるのか。それは「そのように書いている」のでなく、「読者がキャラクタから想像した人物が動き出している」からだという話があります。
つまり、虫歯とピアニストでいえば、ピアニストの大西さんが「ピアニストとして年齢はこれくらいで男性だから」ということで「決め打ち」のキャラクタでないということです。
読者が「書かれた情報から補って自分なりの”大西さん”を生成する。その大西さんがまさに言う台詞であってもおかしくない」からこそ、架空のキャラクタが述べているのでなく、そこにいる実在する大西さんが述べているから、説得力があるのではないか。
アンナもそうだし、若林家の父親もそうだなあと。
家族ってなんだろうとか、ひたすらエモリたい人に
猫ストラップのために手にとった何気ない一冊ですが、大当たりでした(笑)
ひたすらエモいというのは、本当です。一々家族の構成員であるそれぞれの視点が上手く書かれているわけです。とくに主人公がその中でも相対的に丁寧に書かれているのか、リアル感が出ています。
小説というのは言葉で世界を作り出すわけですが、世界の愛し方というか、社会の愛し方というか、そこに浸れるという感じがしました。奥田さんという人は前はもっとコミカルな笑いだった気がするので、こんなにエモいのもいけるのかと感動してしまったわけです。
もちろん家族だから嫌なこともやるとか、良いことばかりではないですよね。全てのストーリーは家族の愛というよりも、どちらかというと家族のあり方という感じです。そういう家族が家族の分だけあるからこそ、タイトルに「ヒミツ」とあるんじゃないかと。これもコピーライターらしいキャッチーな言葉だと刺さりました。
久しぶりに小説読んだからだけかもしれませんが、劇おすすめですね。
筆者プロフィール

- 「シゴクリ」運営者。アイデアの力でお客様に貢献するゼロイチ大好きアイデアマン。ビジネスアイデア相談実績等は200超を超える。好きな言葉は三方良し。詳しい自己紹介、仕事実績も合わせてご覧ください。お仕事メニューやお問い合わせはお気軽にどうぞ。
最新の投稿
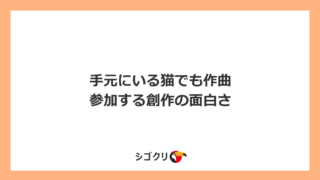 アイデアネタ2024年4月26日手元にいる猫でも作曲参加する創作の面白さ
アイデアネタ2024年4月26日手元にいる猫でも作曲参加する創作の面白さ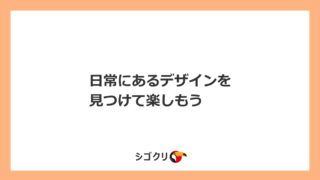 アイデアネタ2024年4月25日日常にあるデザインを見つけて楽しもう
アイデアネタ2024年4月25日日常にあるデザインを見つけて楽しもう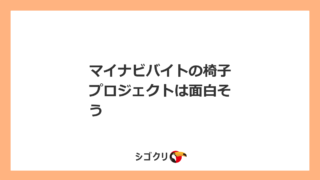 アイデアネタ2024年4月24日マイナビバイトの椅子プロジェクトは面白そう
アイデアネタ2024年4月24日マイナビバイトの椅子プロジェクトは面白そう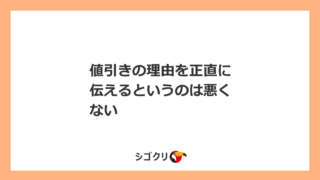 アイデアネタ2024年4月23日値引きの理由を正直に伝えるというのは悪くない
アイデアネタ2024年4月23日値引きの理由を正直に伝えるというのは悪くない
違和感で発想のやり方が学べます
LINE公式アカウント登録で無料で学べます。気になる方はチェックしてみて下さい。